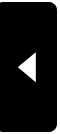› gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › art
› gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › art2011年01月06日
本島入り
2011年明けましておめでとうございます。
明日から通常業務をはじめます。
あしたは7草粥 笠島のお年寄りが、七草粥をふるまってくださいます。
2月の展覧会予定は建築家の平野祐一さんです。
灯りのプランです。詳細は後日改めてアルテのHPにて紹介します。
2月は大阪から大倉邸に滞在してスケッチをしたいという
お客様からの食事のご予約がアルテに入っています。
冬期は、訪れる方が少ないので、ゆっくりしたいのだそうです。
今年も宜しくお願い申し上げます。
明日から通常業務をはじめます。
あしたは7草粥 笠島のお年寄りが、七草粥をふるまってくださいます。
2月の展覧会予定は建築家の平野祐一さんです。
灯りのプランです。詳細は後日改めてアルテのHPにて紹介します。
2月は大阪から大倉邸に滞在してスケッチをしたいという
お客様からの食事のご予約がアルテに入っています。
冬期は、訪れる方が少ないので、ゆっくりしたいのだそうです。
今年も宜しくお願い申し上げます。
2010年12月10日
一年がたった
本島にアルテという現代美術のギャラリーを移転して
ようやく一年がたった。
今朝トシコさんと立ち話をしたおり、もうどうのくらいになる?とトシコさんから
訊ねられた。私が「11月からの移転だったので、一年経ちました。」と応えると
そうのくらいかね。もっと前からのような気がするといわれた。
トシコさん曰く「あんたたちのような若い人が来てくれて、暮らしてくれて
本当にうれしいよ。みんなと仲良くこれからもやっていってよ。」
年を負うごとに人は老いてゆき、人が少なくなる。
この寂しげな町並みは、今年の夏は20代のアーティストたちと暮らしを共にしたことが
人々に刺激になったようだ。作家が島を離れるごとに、港まで見送ってくださる方もあり
島の人々は名残惜しそうだった。
来年もまた新たな人々を迎え入れてと願う人もあって、
なんとか、応えたいと思った。
香川の人にとって、瀬戸内の島の暮らしは近くて遠い。
他府県の特に都市に暮らす人々の方が、この島を魅力的だと感じるようだ。
そんなものなのだろう。
今日は冷える。晴れていて、外は青空、猫は日向ぼっこ。
そして、町並みの人々は畑でジャガイモや大根を収穫している。
私もアルテの左向かいに畑を借りた。畑を耕してもらったら、
玉ちゃんがカリフラワーや豆の苗をもらってきてくれて、植えてくれた。
私も丸亀でタマネギと豆の苗を買ってきて、玉ちゃんに植えつけをお願いした。
毎朝、私が目覚めると畑の苗に水をやっていてくれる。もっと早く起きて私が水遣り
しなくちゃと思って、目覚めると畝は既に水がまかれたあとが残っている。
こうして、草取りから苗を植え付け、果ては水遣りまで、島の方のお世話になりながら
私の畑では、初めての野菜が育っている。
子供の頃、実家の寺の裏庭で祖母の趣味が、畑を栽培すること だったので
多少は手伝い、記憶もあるが、自らではなかったので、全くのド素人の私は、
島の人々の注目を浴びながら、畑づくりをはじめた。
食とアートのプロジェクト 食の部門は、数年がかりのテーマになることだろう。
空き家が多い笠島地区だが、盆と正月には帰省する人々が多いため
なかなか、新たな住人が空き家を借りて活動することが難しいのだが、
人が暮らさない建物は傷みがはやい。建物は人が暮らすことで、初めてその本来の
機能を発揮する。短期間であっても様々若者アーティストが町並みの中で
創作活動を行う。こういうかたちの活性化はこれからの時代には必然となるのでは
ないのかと思う。
ようやく一年がたった。
今朝トシコさんと立ち話をしたおり、もうどうのくらいになる?とトシコさんから
訊ねられた。私が「11月からの移転だったので、一年経ちました。」と応えると
そうのくらいかね。もっと前からのような気がするといわれた。
トシコさん曰く「あんたたちのような若い人が来てくれて、暮らしてくれて
本当にうれしいよ。みんなと仲良くこれからもやっていってよ。」
年を負うごとに人は老いてゆき、人が少なくなる。
この寂しげな町並みは、今年の夏は20代のアーティストたちと暮らしを共にしたことが
人々に刺激になったようだ。作家が島を離れるごとに、港まで見送ってくださる方もあり
島の人々は名残惜しそうだった。
来年もまた新たな人々を迎え入れてと願う人もあって、
なんとか、応えたいと思った。
香川の人にとって、瀬戸内の島の暮らしは近くて遠い。
他府県の特に都市に暮らす人々の方が、この島を魅力的だと感じるようだ。
そんなものなのだろう。
今日は冷える。晴れていて、外は青空、猫は日向ぼっこ。
そして、町並みの人々は畑でジャガイモや大根を収穫している。
私もアルテの左向かいに畑を借りた。畑を耕してもらったら、
玉ちゃんがカリフラワーや豆の苗をもらってきてくれて、植えてくれた。
私も丸亀でタマネギと豆の苗を買ってきて、玉ちゃんに植えつけをお願いした。
毎朝、私が目覚めると畑の苗に水をやっていてくれる。もっと早く起きて私が水遣り
しなくちゃと思って、目覚めると畝は既に水がまかれたあとが残っている。
こうして、草取りから苗を植え付け、果ては水遣りまで、島の方のお世話になりながら
私の畑では、初めての野菜が育っている。
子供の頃、実家の寺の裏庭で祖母の趣味が、畑を栽培すること だったので
多少は手伝い、記憶もあるが、自らではなかったので、全くのド素人の私は、
島の人々の注目を浴びながら、畑づくりをはじめた。
食とアートのプロジェクト 食の部門は、数年がかりのテーマになることだろう。
空き家が多い笠島地区だが、盆と正月には帰省する人々が多いため
なかなか、新たな住人が空き家を借りて活動することが難しいのだが、
人が暮らさない建物は傷みがはやい。建物は人が暮らすことで、初めてその本来の
機能を発揮する。短期間であっても様々若者アーティストが町並みの中で
創作活動を行う。こういうかたちの活性化はこれからの時代には必然となるのでは
ないのかと思う。
2010年11月09日
人間の運命
只今は私は、笠島のアルテに一人、何ヶ月ぶりかのひっそりとした時間をすごしている。
夏の猛暑は思い出となり、冬の寒さが日ごとにますこの頃。
今日の瀬戸内の海はというと、冬の寒風で白波がたち、小さな高速艇は、左右に大きく
傾き、波が窓にザブンザブンと打ち付ける中の航行だった。
日中2便は運行取りやめとなっていた。「このまま20分もジェットコースター状態は
勘弁してよ。」と思わず言ってみても、乗り込んでしまったのだから、仕方がない。
咸臨丸は35日間が荒波だったと記録にあったが、さぞかし不安だったろう
などと考えて過ごした。
先日11月6日松宮硝子さんが笠島を離れ、作家の滞在制作はひとまず終了した。
展覧会は11月28日まで、私は、あと数十日は、まだまだ月火の休みを返上したかたちで
ひたすら咸臨丸ランチづくりとギャラリー業務に追われる日々が続く。
本当に10月は、多忙な月だった。月火の休みが取れぬまま、11月になだれ込んだ。
さらには咸臨丸150周年記念の行事もあって多くの人々が笠島やアルテを訪ねてくださるが、
そのため、11月7日まで全く休暇をとることが出来ないまま、
笠島に滞在することになってしまったのだ。
さらに、7月からの作家との日々のやりとり主にドタバタであるが、
ブログにアップできなかったことは、悔しい限り。
多忙の始まりは、大倉邸に3.4日滞在して笠島を描きたいという人々だった。
ついては食事の方をアルテでよろしく頼みたい。
10日の展覧会を目前に控え、通常でも早朝から訪れる人々の対応に
終始し、ただでもギャラリー業務が滞っているのに・・。
お客様は、刺激的な人々であって、
肉体的にはきつい日々だったが、精神的には緊張感が楽しかった。
そのお一人から先日11月5日一冊の本が贈られてきた。
「よど号」事件三十年目の真実 対策本部事務局長の回想
島田滋敏/著
出版社名 草思社
というものだった。
島田さんは、昨年笠島を訪れていただいた白金台にお住まいの某社長のご友人。
その某社長、東京で笠島や笠島に移転したアルテを皆さんに
薦めてくださるものだから、島田さんが、興味を持ってくださって、
以来のご縁の方。
島田滋敏 さんは、S45年、「よど号」事件の当時、日航の対策本部事務局長として、
陣頭指揮をとられた方。 福岡での給油後、ピョンヤンに向けて飛び立ったはずの
「よど号」はなぜ、ソウル金浦空港に降りたのか。「金浦偽装着陸」について
当時は語ることが出来なかった事件の真実について、
当事者であるからこそ、30年後の今語ることに胸つかれる。
様々な想いが巡る。
また石田機長のその後の人生の変化を知ることとなった。
人間の運命というものを考える。
改めて、一期一会を深く胸に刻む。
時間は常に流れてゆく。
その瞬間に燃焼できているか。
怠惰に過ごしていないか。
夏の猛暑は思い出となり、冬の寒さが日ごとにますこの頃。
今日の瀬戸内の海はというと、冬の寒風で白波がたち、小さな高速艇は、左右に大きく
傾き、波が窓にザブンザブンと打ち付ける中の航行だった。
日中2便は運行取りやめとなっていた。「このまま20分もジェットコースター状態は
勘弁してよ。」と思わず言ってみても、乗り込んでしまったのだから、仕方がない。
咸臨丸は35日間が荒波だったと記録にあったが、さぞかし不安だったろう
などと考えて過ごした。
先日11月6日松宮硝子さんが笠島を離れ、作家の滞在制作はひとまず終了した。
展覧会は11月28日まで、私は、あと数十日は、まだまだ月火の休みを返上したかたちで
ひたすら咸臨丸ランチづくりとギャラリー業務に追われる日々が続く。
本当に10月は、多忙な月だった。月火の休みが取れぬまま、11月になだれ込んだ。
さらには咸臨丸150周年記念の行事もあって多くの人々が笠島やアルテを訪ねてくださるが、
そのため、11月7日まで全く休暇をとることが出来ないまま、
笠島に滞在することになってしまったのだ。
さらに、7月からの作家との日々のやりとり主にドタバタであるが、
ブログにアップできなかったことは、悔しい限り。
多忙の始まりは、大倉邸に3.4日滞在して笠島を描きたいという人々だった。
ついては食事の方をアルテでよろしく頼みたい。
10日の展覧会を目前に控え、通常でも早朝から訪れる人々の対応に
終始し、ただでもギャラリー業務が滞っているのに・・。
お客様は、刺激的な人々であって、
肉体的にはきつい日々だったが、精神的には緊張感が楽しかった。
そのお一人から先日11月5日一冊の本が贈られてきた。
「よど号」事件三十年目の真実 対策本部事務局長の回想
島田滋敏/著
出版社名 草思社
というものだった。
島田さんは、昨年笠島を訪れていただいた白金台にお住まいの某社長のご友人。
その某社長、東京で笠島や笠島に移転したアルテを皆さんに
薦めてくださるものだから、島田さんが、興味を持ってくださって、
以来のご縁の方。
島田滋敏 さんは、S45年、「よど号」事件の当時、日航の対策本部事務局長として、
陣頭指揮をとられた方。 福岡での給油後、ピョンヤンに向けて飛び立ったはずの
「よど号」はなぜ、ソウル金浦空港に降りたのか。「金浦偽装着陸」について
当時は語ることが出来なかった事件の真実について、
当事者であるからこそ、30年後の今語ることに胸つかれる。
様々な想いが巡る。
また石田機長のその後の人生の変化を知ることとなった。
人間の運命というものを考える。
改めて、一期一会を深く胸に刻む。
時間は常に流れてゆく。
その瞬間に燃焼できているか。
怠惰に過ごしていないか。
2010年10月01日
2010年09月11日
2010年08月13日
笠島のお盆
知己の画廊からは夏季休廊のお知らせをいただくが
笠島にあるアルテはお盆時期こそ仕事の時間
いつもはひっそりとした笠島の夜が、今夜は
あちこちの家に灯りが そして人の話し声
今日もアルテはお盆で里帰りをしたという人々の来訪でにぎわった。
竹紙づくりの柴田君の助っ人も加わり、アルテの人の出入りが
いつもと異なった人々の来訪でにぎわう。
実は自転車で帰る途中。下り坂の坂道で自転車で転倒。
左側のあちこちを負傷したため、12日まで休養していた。
まだ手は使えないので、この時期の助っ人は本当にありがたい。
東京理科大の長井君も友人と今日から本島に滞在していると
訪ねてくれた。若い人が行き交うので、笠島のお年よりは
とてもうれしそう。
いつもの本島とは違った表情の本島もなかなかいいものだ。
笠島にあるアルテはお盆時期こそ仕事の時間
いつもはひっそりとした笠島の夜が、今夜は
あちこちの家に灯りが そして人の話し声
今日もアルテはお盆で里帰りをしたという人々の来訪でにぎわった。
竹紙づくりの柴田君の助っ人も加わり、アルテの人の出入りが
いつもと異なった人々の来訪でにぎわう。
実は自転車で帰る途中。下り坂の坂道で自転車で転倒。
左側のあちこちを負傷したため、12日まで休養していた。
まだ手は使えないので、この時期の助っ人は本当にありがたい。
東京理科大の長井君も友人と今日から本島に滞在していると
訪ねてくれた。若い人が行き交うので、笠島のお年よりは
とてもうれしそう。
いつもの本島とは違った表情の本島もなかなかいいものだ。
2010年08月07日
あかねとんぼ
8月に入って、ここ本島では朝夕の風が変った。
アルテの前の東小路には、あかねトンボが飛び交っている。
日中はまだまだ日差しは厳しいのだが、秋の気配が漂っている・・
自然の中で深く暮らすと、季節の移り変わりを空気の気配で体感している。
レジデンスアーティストの一人、山田健二さんが、面白い着想で遺すことを前提に
作品化を図っている。
******『使用と地上の保存学』*********山田健二
笠島に初めてバスで降り立った時の印象を今でも忘れない。時間の突き当たりというか、
曲がり角に立ったような感覚と、町と港を隔てる道路が不思議にも大きな彼岸に見えて、
居たたまれずに妙な積極性で町に滑り込んだのだった。石畳が降り積もったような拡がり
に、細く降る様々な色と建材の残像を見るような風景は知識や写真では推し量れない印象
で、こころの底をほどいていくようだった。その奥で東北や北陸の山村に消えた茅葺き屋
根の町並みを思い、うらやむ気持ちもこみ上げてくる。
その印象と風景にわたしは深く敬服しながら町を巡り、兼ねてから思う“ 使うことの保存”
への関心と意味をその風景に沈めていった。
本島に住んで1ヶ月になろうとしている。顔なじみもできて、生活や暮らしの隣人も増
えた。今では笠島の塩飽大工である高島昭夫氏が初めてお会いした日に話していた「古い
建築を本当に保存しようと思ったら、古い生活のままでいなければならなくなる。」と言う
言葉の解釈にいろいろな表情が増してきたように思う。一つは解釈に切実さと痛みを伴っ
てきた事だろうか。古い慣習や作法、信仰と結びついた間取りや建築の造りそのものは土
地や環境からの交渉を受け止め、抗し、包み込むための器でもある。その内と外の境界は
外環境への堅固さを追求した現代建築と比べると真実でしか保てない程 繊細なものなのだ
と今では強く感じるようになっていた。
制作活動の現場や住居の為の物件が中々に見つからなかった折に、昭夫さんは簡単では
ない島を出た家主の心情をいろいろと話してくれた。「なかにはここに住んでいたと言える
何かがあればそれでいいと言う人もいる。」倒壊を待つように放置された邸宅の家主の思い
を語ったであろうその言葉は、使うことの保存学の向こうで今 変わろうとしているひとの
気持ちを痛感させるものだった。
山のすそ野に呑み込まれようとしている古い家屋の構造や、それを貫くように湧き立つ
生命を見ながら、親族達で使うということからは又違う未来の選択がそこにはあるように
も感じる。人が住まい、暮らすということから植物や他のあらゆる生命にその‘使用’ の間
口を開かれたその“ 場” は公の庭園である“ 公園” を超えて庭園のもつ本来的な、そして
未来的な在り方へと繋がる覗き穴のようにも感じられた。」
保存地区で実践される“ 使用の保存学” が転じて照らし出した新しい保存と共存のこころ
は、都市や地域社会に於ける建築と環境の共存と双方からの組織化の未来に全く新しい示
唆をもたらすものであると感じてやまない。
① 植物と重なる構造(植生)
植物にとっての建築、構造のーザビリティーや現状の植
生をリサーチし刈り込みや植林などの計画を検討する。
植物と一体のとなる家屋を樹木に見立て、敷地に庭園を作庭する。
真木邸を計画室とし各部屋にテーマ別の模型、図面、写真を空間の中に編集、表現する。
隔てられてはいるもののそれぞれに隣接した部屋の要素は編集の過程で交雑する。
② 風、暮らしと時間の通態(構造)
家屋の空間的構造と間取りの意味、現状の構造補強(?) を検討する。
③ 田中小路、山、街路と地形(フィールド)
西山や街路との関係性から敷地を隔てる壁や敷地の起伏等を設計する。
作品化の為の資金調達を、丸亀市文化課冨田さんとともに、図る。
昨日は、梅谷の*回目の誕生日。サプライズでみんながケーキととんかつで
祝ってくださった。お隣の吉田愛子さんも参加して、愛子さんはこうして
若い作家たちとの夕食がとても楽しい様子。一人で食べるよりは
大勢で食卓を囲むと楽しいよね。
お年寄りの一人暮らし。こういった形で世代を超えて場をひとつにすること
これが私がここで試みたかったひとつだと改めて思う。
耕すとは、ひとりひとりのこころを耕して行く事でもあるのだから。
アルテの前の東小路には、あかねトンボが飛び交っている。
日中はまだまだ日差しは厳しいのだが、秋の気配が漂っている・・
自然の中で深く暮らすと、季節の移り変わりを空気の気配で体感している。
レジデンスアーティストの一人、山田健二さんが、面白い着想で遺すことを前提に
作品化を図っている。
******『使用と地上の保存学』*********山田健二
笠島に初めてバスで降り立った時の印象を今でも忘れない。時間の突き当たりというか、
曲がり角に立ったような感覚と、町と港を隔てる道路が不思議にも大きな彼岸に見えて、
居たたまれずに妙な積極性で町に滑り込んだのだった。石畳が降り積もったような拡がり
に、細く降る様々な色と建材の残像を見るような風景は知識や写真では推し量れない印象
で、こころの底をほどいていくようだった。その奥で東北や北陸の山村に消えた茅葺き屋
根の町並みを思い、うらやむ気持ちもこみ上げてくる。
その印象と風景にわたしは深く敬服しながら町を巡り、兼ねてから思う“ 使うことの保存”
への関心と意味をその風景に沈めていった。
本島に住んで1ヶ月になろうとしている。顔なじみもできて、生活や暮らしの隣人も増
えた。今では笠島の塩飽大工である高島昭夫氏が初めてお会いした日に話していた「古い
建築を本当に保存しようと思ったら、古い生活のままでいなければならなくなる。」と言う
言葉の解釈にいろいろな表情が増してきたように思う。一つは解釈に切実さと痛みを伴っ
てきた事だろうか。古い慣習や作法、信仰と結びついた間取りや建築の造りそのものは土
地や環境からの交渉を受け止め、抗し、包み込むための器でもある。その内と外の境界は
外環境への堅固さを追求した現代建築と比べると真実でしか保てない程 繊細なものなのだ
と今では強く感じるようになっていた。
制作活動の現場や住居の為の物件が中々に見つからなかった折に、昭夫さんは簡単では
ない島を出た家主の心情をいろいろと話してくれた。「なかにはここに住んでいたと言える
何かがあればそれでいいと言う人もいる。」倒壊を待つように放置された邸宅の家主の思い
を語ったであろうその言葉は、使うことの保存学の向こうで今 変わろうとしているひとの
気持ちを痛感させるものだった。
山のすそ野に呑み込まれようとしている古い家屋の構造や、それを貫くように湧き立つ
生命を見ながら、親族達で使うということからは又違う未来の選択がそこにはあるように
も感じる。人が住まい、暮らすということから植物や他のあらゆる生命にその‘使用’ の間
口を開かれたその“ 場” は公の庭園である“ 公園” を超えて庭園のもつ本来的な、そして
未来的な在り方へと繋がる覗き穴のようにも感じられた。」
保存地区で実践される“ 使用の保存学” が転じて照らし出した新しい保存と共存のこころ
は、都市や地域社会に於ける建築と環境の共存と双方からの組織化の未来に全く新しい示
唆をもたらすものであると感じてやまない。
① 植物と重なる構造(植生)
植物にとっての建築、構造のーザビリティーや現状の植
生をリサーチし刈り込みや植林などの計画を検討する。
植物と一体のとなる家屋を樹木に見立て、敷地に庭園を作庭する。
真木邸を計画室とし各部屋にテーマ別の模型、図面、写真を空間の中に編集、表現する。
隔てられてはいるもののそれぞれに隣接した部屋の要素は編集の過程で交雑する。
② 風、暮らしと時間の通態(構造)
家屋の空間的構造と間取りの意味、現状の構造補強(?) を検討する。
③ 田中小路、山、街路と地形(フィールド)
西山や街路との関係性から敷地を隔てる壁や敷地の起伏等を設計する。
作品化の為の資金調達を、丸亀市文化課冨田さんとともに、図る。
昨日は、梅谷の*回目の誕生日。サプライズでみんながケーキととんかつで
祝ってくださった。お隣の吉田愛子さんも参加して、愛子さんはこうして
若い作家たちとの夕食がとても楽しい様子。一人で食べるよりは
大勢で食卓を囲むと楽しいよね。
お年寄りの一人暮らし。こういった形で世代を超えて場をひとつにすること
これが私がここで試みたかったひとつだと改めて思う。
耕すとは、ひとりひとりのこころを耕して行く事でもあるのだから。
2010年07月08日
はじめまして。柴田です。
どーもはじめまして柴田と申します。
昨日、7月7日に香川県の本島、笠島に到着しました。
これから、2ヶ月間、こちら現代美術のギャラリー、ギャラリーアルテで滞在し、地域とふれあい、作品をつくります。
昼間はこれから宿泊させていただく民家をお掃除して、
夜、水墨画を描きました。
いつもこのあたりでうろうろしています。
皆様、こちらにお越ししていただける機会がございましたら
ぜひ遊んでやってください。
柴田 智明
昨日、7月7日に香川県の本島、笠島に到着しました。
これから、2ヶ月間、こちら現代美術のギャラリー、ギャラリーアルテで滞在し、地域とふれあい、作品をつくります。
昼間はこれから宿泊させていただく民家をお掃除して、
夜、水墨画を描きました。
いつもこのあたりでうろうろしています。
皆様、こちらにお越ししていただける機会がございましたら
ぜひ遊んでやってください。
柴田 智明
2010年07月06日
本島に居候させていただきます。
はじめましてこんばんは。
今日から本島で滞在する佐藤佳紀と申します。
僕は今まで10回以上本島を訪ねましたが、一夜を明かすのは今日が初めてです。
さっきギャラリーの外へでて石畳の通りで夜風に当たってきましたが、静かで星の瞬きが綺麗でした。
和風家屋の立ち並ぶ笠島地区の夜空は、自動車の往来する音もなく視界を遮る電線もなく風情があります。
明け方から夕暮れまでは鳥のさえずりが響いているので、明日の朝が楽しみです。
これからARTEさんにお世話になりつつ、本島のひとたちと交流できればいいなと考えています。
自分がどういう切り口で関れるかはまだまだわかりませんが、とりあえず島の仕事やARTEさんの手伝いをしていこうと思います。
この場所ではひとの暮らしや営みが生身で感じられるような気がして、これからの滞在がとても楽しみです。
まだ学生の若輩者ですが、先輩方に学びながらよい経験としたいです。
今日から本島で滞在する佐藤佳紀と申します。
僕は今まで10回以上本島を訪ねましたが、一夜を明かすのは今日が初めてです。
さっきギャラリーの外へでて石畳の通りで夜風に当たってきましたが、静かで星の瞬きが綺麗でした。
和風家屋の立ち並ぶ笠島地区の夜空は、自動車の往来する音もなく視界を遮る電線もなく風情があります。
明け方から夕暮れまでは鳥のさえずりが響いているので、明日の朝が楽しみです。
これからARTEさんにお世話になりつつ、本島のひとたちと交流できればいいなと考えています。
自分がどういう切り口で関れるかはまだまだわかりませんが、とりあえず島の仕事やARTEさんの手伝いをしていこうと思います。
この場所ではひとの暮らしや営みが生身で感じられるような気がして、これからの滞在がとても楽しみです。
まだ学生の若輩者ですが、先輩方に学びながらよい経験としたいです。
2010年07月06日
滞在作家本島入り
決まっていた作家滞在住宅がドタキャンで絶体絶命のピンチ
プロジェクトの開催も危ぶまれほとほと困っていたところ
島で懇意の人々の奔走でなんとかギリギリで住まうところが確保できました
今日、明日、11日と次々に作家たちが入ってきます
まずはおうちのお掃除から
これからまた今まで通りの活動と新しい活動が粛々と始まります
報告
長岡まき子
プロジェクトの開催も危ぶまれほとほと困っていたところ
島で懇意の人々の奔走でなんとかギリギリで住まうところが確保できました
今日、明日、11日と次々に作家たちが入ってきます
まずはおうちのお掃除から
これからまた今まで通りの活動と新しい活動が粛々と始まります
報告
長岡まき子
2010年06月30日
人生のピンチ
立ち止まったとき
映画 キャッチーボール屋を見る。
キャッチボールできる相手がいない方には
キャッチボール屋を。。
只今私の周りには、欲望がないか または欲望の薄い人が伴走してくれています。
強欲な方は とうに立ち去っています。
良かった。。
映画 キャッチーボール屋を見る。
キャッチボールできる相手がいない方には
キャッチボール屋を。。
只今私の周りには、欲望がないか または欲望の薄い人が伴走してくれています。
強欲な方は とうに立ち去っています。
良かった。。
2010年06月25日
2010年06月23日
早起き
本島の朝は早い。
5時ごろ起きて、畑仕事をはじめている。
10時40分のフェリーに乗ると本島には、11時15分につく。
港から自転車で6分 そこで 私の店は、11時30分開店に
しているが、本島に泊っているときは、夜中にギャラリーの仕事をしようとして
夜更かしをして9時起床が多かった。
実際はもっと早くに目覚めているのだが、木戸を開くと誰かかが訪ねてくる。
そうすると、自分のペースが朝から狂うので、木戸は固く締めていた。
締めていても、裏口から声がかかる。中には木戸越しに声がかかる。
だから、夜は早く眠って、朝早く起きて、仕事を始めることにした。
朝方に変えて行かないと、かえってストレスが溜まることに気づいた。
島の朝は爽快だ。昨夜の雨が晴れた朝の空気はひやりとして
清浄な空気だ。
7月からアーテティストイン・レジデンスがはじまる。
彼ら(彼女)たちは、どんな日常をここで過ごすことになるのだろう。
島の人々も楽しみにしているようだから、きっとほっといてくれないだろう。
なじんでいってくれるといいが。。
5時ごろ起きて、畑仕事をはじめている。
10時40分のフェリーに乗ると本島には、11時15分につく。
港から自転車で6分 そこで 私の店は、11時30分開店に
しているが、本島に泊っているときは、夜中にギャラリーの仕事をしようとして
夜更かしをして9時起床が多かった。
実際はもっと早くに目覚めているのだが、木戸を開くと誰かかが訪ねてくる。
そうすると、自分のペースが朝から狂うので、木戸は固く締めていた。
締めていても、裏口から声がかかる。中には木戸越しに声がかかる。
だから、夜は早く眠って、朝早く起きて、仕事を始めることにした。
朝方に変えて行かないと、かえってストレスが溜まることに気づいた。
島の朝は爽快だ。昨夜の雨が晴れた朝の空気はひやりとして
清浄な空気だ。
7月からアーテティストイン・レジデンスがはじまる。
彼ら(彼女)たちは、どんな日常をここで過ごすことになるのだろう。
島の人々も楽しみにしているようだから、きっとほっといてくれないだろう。
なじんでいってくれるといいが。。
2010年06月13日
和して同ぜず
「和して同ぜず」これに尽きる。
本島でギャラリーを展開して、気づくと半年たった。
NHKの旬感香川というコーナーでここでのギャラリーの活動
地域の人々との交流の様子を紹介された。
放送を見て、また送られてきたDVDを島の人が見に来られて
改めて、しみじみ考えた。
「和して同ぜず」これに尽きる・・。
ギャラリーとしての時間と島の人々が求め、関ってくる時間とのせめぎあいがあった。
まずは、島人との交流を先に、私を透明にした半年間。。
7月からはギャラリーの時間を日中に作り出したい。
私の中ではせめぎあい。。
「曽子(そうし)曰く、士(し)は以て弘毅(こうき)ならざるべからず。
任(にん)重(おも)くして道(みち)遠(とお)し。
仁(じん)以て己(おの)が任と為(な)す。亦(また)重からずや。
死(し)して後(のち)己(や)む。亦遠からずや。」
意味
曽子が言いました。
「リーダーというものは、広い器量と強い意志を持たなければならない。
リーダーの責任は重く、進むべき道のりは遠い。
仁(思いやり)の心を持って、初めてその責任を果たすことが出来る。
何と責任の重いことなのだろうか。
その責任は死んで初めて開放されるのである。
何と道のりの遠いことなのだろうか」と。
ああ・・
本島でギャラリーを展開して、気づくと半年たった。
NHKの旬感香川というコーナーでここでのギャラリーの活動
地域の人々との交流の様子を紹介された。
放送を見て、また送られてきたDVDを島の人が見に来られて
改めて、しみじみ考えた。
「和して同ぜず」これに尽きる・・。
ギャラリーとしての時間と島の人々が求め、関ってくる時間とのせめぎあいがあった。
まずは、島人との交流を先に、私を透明にした半年間。。
7月からはギャラリーの時間を日中に作り出したい。
私の中ではせめぎあい。。
「曽子(そうし)曰く、士(し)は以て弘毅(こうき)ならざるべからず。
任(にん)重(おも)くして道(みち)遠(とお)し。
仁(じん)以て己(おの)が任と為(な)す。亦(また)重からずや。
死(し)して後(のち)己(や)む。亦遠からずや。」
意味
曽子が言いました。
「リーダーというものは、広い器量と強い意志を持たなければならない。
リーダーの責任は重く、進むべき道のりは遠い。
仁(思いやり)の心を持って、初めてその責任を果たすことが出来る。
何と責任の重いことなのだろうか。
その責任は死んで初めて開放されるのである。
何と道のりの遠いことなのだろうか」と。
ああ・・
2010年06月10日
本島自治会長 会
写真は、子猫の元気とそのおかあちゃんのくろちゃん。
なんと安心しきった寝姿。。
今日は実に紫外線の厳しい日でした。
午後1時半から 支所で本島連合自治会長会議が開かれ
その席上で、7月から本格的にはじまるアートプロジェクトの説明を
行いました。
竹紙については、興味深く質問がありました。
自治会長から各自治会員へ周知、ボランティア等の
島内協力者を計っていただきます。
只今Webデザインの担当者を募集しています。
Web制作、情報更新は本島在住のじょうじ丸さんにご参加いただき
お願いしたいと昨日ご相談しました。理科物理に強いIターンの方です。
高知生まれ、いごっそうです。
2010年06月03日
2010年05月29日
竹紙づくり
一昨日から、竹紙づくりのために、里山へはいって若竹を切り出しています。
笠島も周囲に竹林が広がっていて、竹はそのまま放置すると
どんどん畑を侵食してしまうのです。
竹紙は、中国から伝わったものですが、薄いのですが、墨書には
向いているようですので、レジデンシー予定作家に依頼して
これから一緒に作って行こうと思います。
淡竹(はちく)いただきました。アクが少なく冷凍保存もできる食材です。
そらまめ、鯛をいただきました。
明日はまたNHKの方が取材にいらっしゃいます。
半年たちました。週5日本島で暮らしてみることで暮らしの様子がわかってきます。
いろいろなところから訪れる人が多いです。
もっとのんびり過ごせると考えていたのですが、丸亀でギャラリー開いているときよりも
朝から終日ご近所の方を含めて、毎日いろいろな方が訪れ
なんだかあわただしく過ごしてしまいます。
すれていない料理を作っているので、手間もかかって
キッチンにたつ時間が長いです。
猫もあいかわらず、戸口で待ち受けています。
笠島も周囲に竹林が広がっていて、竹はそのまま放置すると
どんどん畑を侵食してしまうのです。
竹紙は、中国から伝わったものですが、薄いのですが、墨書には
向いているようですので、レジデンシー予定作家に依頼して
これから一緒に作って行こうと思います。
淡竹(はちく)いただきました。アクが少なく冷凍保存もできる食材です。
そらまめ、鯛をいただきました。
明日はまたNHKの方が取材にいらっしゃいます。
半年たちました。週5日本島で暮らしてみることで暮らしの様子がわかってきます。
いろいろなところから訪れる人が多いです。
もっとのんびり過ごせると考えていたのですが、丸亀でギャラリー開いているときよりも
朝から終日ご近所の方を含めて、毎日いろいろな方が訪れ
なんだかあわただしく過ごしてしまいます。
すれていない料理を作っているので、手間もかかって
キッチンにたつ時間が長いです。
猫もあいかわらず、戸口で待ち受けています。
2010年05月24日
昨日は本島で打ち上げ
23日京都から中屋敷智生君 岡山から真部剛一君
が夕方から本島入り。
高島さんを交え、夜はアルテで打ち上げパーティーを行いました。
新たまねぎのカツを美味い美味いと食べ、久しぶりにアートの話題で
夜も更けました。
合宿は4年前を彷彿とし、なつかしくもあり
また、これからの本島笠島でのありようを考えた一日でした。
が夕方から本島入り。
高島さんを交え、夜はアルテで打ち上げパーティーを行いました。
新たまねぎのカツを美味い美味いと食べ、久しぶりにアートの話題で
夜も更けました。
合宿は4年前を彷彿とし、なつかしくもあり
また、これからの本島笠島でのありようを考えた一日でした。
2010年05月22日
瀬戸内海文化助成発表大会
瀬戸内海文化助成発表大会が高松サンポートホールで開催されたので、久しぶりに高松へ。
13:00-17:00まで30組の研究発表が行われました。
今夜から明日にかけて雨模様なので、急いで戻り、最終便で本島へ入りました。
「おう。いまから本島?」と声をかけられ、高島さん、吉田夫妻とも一緒の船で本島へ。
福武財団の瀬戸内海文化助成によって、瀬戸内海の様々な姿が浮かびあがっていることを
はじめて知る機会となりました。
学術研究は質の高い研究が多く、発表も皆さん4分間の時間内によくまとめられており、
また短い時間の中で、研究への興味がそそられるものでした。素晴らしかったです。
活動の部門では、文楽の上演や歌舞伎の口上を交えたもの。
映画のシーンを編集したものなど、パワーポイントを使いこなしたものが多く見られ、
久々にいい刺激を受けることができました。
審査員の講評では、今年は特に地理と歴史文化に対して目が向けられているのではないか?ということ。
また場所の記憶 景観の背後にある歴史や文化へのまなざしが自然科学的な態度で向き合っているということでした。
本島での活動を共有していただく仲間と瀬戸内海文化について、
共有しておきたいことだと感じました。いただいた資料を共有したいと感じました。
つづく
13:00-17:00まで30組の研究発表が行われました。
今夜から明日にかけて雨模様なので、急いで戻り、最終便で本島へ入りました。
「おう。いまから本島?」と声をかけられ、高島さん、吉田夫妻とも一緒の船で本島へ。
福武財団の瀬戸内海文化助成によって、瀬戸内海の様々な姿が浮かびあがっていることを
はじめて知る機会となりました。
学術研究は質の高い研究が多く、発表も皆さん4分間の時間内によくまとめられており、
また短い時間の中で、研究への興味がそそられるものでした。素晴らしかったです。
活動の部門では、文楽の上演や歌舞伎の口上を交えたもの。
映画のシーンを編集したものなど、パワーポイントを使いこなしたものが多く見られ、
久々にいい刺激を受けることができました。
審査員の講評では、今年は特に地理と歴史文化に対して目が向けられているのではないか?ということ。
また場所の記憶 景観の背後にある歴史や文化へのまなざしが自然科学的な態度で向き合っているということでした。
本島での活動を共有していただく仲間と瀬戸内海文化について、
共有しておきたいことだと感じました。いただいた資料を共有したいと感じました。
つづく
2010年05月15日
トマトの植え付け
妹尾さんと岡さんが、トマトの苗を植えつけてくださいました。
畑とアルテが、少し遠いので、プランターに植え替えて
アルテの裏庭で育てることになりました。
カントリーガール デビュー
草抜きの手伝いをしました。子猫を自転車のかごに乗せて
畑へ行ったところ、嫌がって突然畑をかけまわって
茂みに逃げ込んで隠れてしまいました。
ドンくさい猫なので、きっと戻ってこれないだろうと
えさでつったり、呼びかけたりして
やっと確保して、連れ帰りました。猫を畑へ連れ出すのはやめます。
笠島中の人が子猫をみかけては
「あんた。。どこまでいっとったんか?」と話しかけています。
みんな 知ってる・・・。こわ・・・。
2010年05月07日
食とアートのプロジェクト準備進行中
本日本島連合自治会会長宮本孝氏 顧問織部氏のお二人に今年後半からはじまる
食とアートのプロジェクト
アーティスト・イン塩飽本島 『~晴れに耕す。そしてアート~』について
ご支援を依頼しました。5月末本島連合自治会総会にて説明会を行わせていただきます。
明日はNPO笠島町並み保存協力会の総会が開催されますので、
その席上でもご説明をさせていただきます。
以下簡単な事業概要です。
ボランティアの募集も行います。この活動に加わっていただきたく、
再度、掲載いたします。
このたび、瀬戸内海文化助成を実施している財)福武学術文化振興財団から本島でのアート活動に対して、助成を受けることとなりました。
今回は、芸術文化を取り入れた豊かな生活が日常的にできるよう、食とアートをテーマとした、地域の人々との交流を生み出すことを目的としています。
7月より11月の期間、2つの計画【A食・野菜栽培 + Bアートの展開】を実施します。「Art Love Food」というテーマに沿った内容の創作を行うアーティスト2名が本島に滞在します。滞在中、地域の文化、環境などからアイディアを得て、創作活動を行い、新たな作品を通じて『住民への飲食の場づくり』『土産物づくり』に繫がるアクションを行います。創作活動とともに、その成果発表や地域との交流プログラムなど複数の作家の参加により行う予定です。
目的)
人と人とが出会い、繋がり、感性を交換することで新しい概念が生まれるというアートの視点から、市民の日常に新たな芸術文化の可能性を探っています。
アーティストが地域に滞在し、創作するという関りから、食や日常を再発見し、本島の魅力を探ろうと考えています。それぞれの存在が、それぞれの地域において「かけがえのない存在」であることを感じられるように、アーティストや全国のサポーターと連携し、ここにしかない関係性を紡いでいきたいという思いです。
さらにこれら、一連の活動と情報をインターネットによって配信することにより、本島という島の暮らし、島で取れる食材の豊かさを発信し、島と県の内外をつなぐ双方向な交流をつくりだすことを目指しています。
内容)
【Aの活動】 6月から食と野菜栽培の活動
【Bの活動】 美術作家が滞在し作品を創作する。アーティスト・イン・レジデンスを行います。
期間)7月・8月 の2ヵ月間 2名のアーティストが滞在し、創作活動を行います。いずれも長期コラボレーションや特別な場所でのワークショップを基本にし、多くの高齢者や子どもを含めた市民に表現活動を提供します。
そして、10月・11月の期間(予定) 成果の発表という形で、展覧会を開催します。
食とアートのプロジェクト
アーティスト・イン塩飽本島 『~晴れに耕す。そしてアート~』について
ご支援を依頼しました。5月末本島連合自治会総会にて説明会を行わせていただきます。
明日はNPO笠島町並み保存協力会の総会が開催されますので、
その席上でもご説明をさせていただきます。
以下簡単な事業概要です。
ボランティアの募集も行います。この活動に加わっていただきたく、
再度、掲載いたします。
このたび、瀬戸内海文化助成を実施している財)福武学術文化振興財団から本島でのアート活動に対して、助成を受けることとなりました。
今回は、芸術文化を取り入れた豊かな生活が日常的にできるよう、食とアートをテーマとした、地域の人々との交流を生み出すことを目的としています。
7月より11月の期間、2つの計画【A食・野菜栽培 + Bアートの展開】を実施します。「Art Love Food」というテーマに沿った内容の創作を行うアーティスト2名が本島に滞在します。滞在中、地域の文化、環境などからアイディアを得て、創作活動を行い、新たな作品を通じて『住民への飲食の場づくり』『土産物づくり』に繫がるアクションを行います。創作活動とともに、その成果発表や地域との交流プログラムなど複数の作家の参加により行う予定です。
目的)
人と人とが出会い、繋がり、感性を交換することで新しい概念が生まれるというアートの視点から、市民の日常に新たな芸術文化の可能性を探っています。
アーティストが地域に滞在し、創作するという関りから、食や日常を再発見し、本島の魅力を探ろうと考えています。それぞれの存在が、それぞれの地域において「かけがえのない存在」であることを感じられるように、アーティストや全国のサポーターと連携し、ここにしかない関係性を紡いでいきたいという思いです。
さらにこれら、一連の活動と情報をインターネットによって配信することにより、本島という島の暮らし、島で取れる食材の豊かさを発信し、島と県の内外をつなぐ双方向な交流をつくりだすことを目指しています。
内容)
【Aの活動】 6月から食と野菜栽培の活動
【Bの活動】 美術作家が滞在し作品を創作する。アーティスト・イン・レジデンスを行います。
期間)7月・8月 の2ヵ月間 2名のアーティストが滞在し、創作活動を行います。いずれも長期コラボレーションや特別な場所でのワークショップを基本にし、多くの高齢者や子どもを含めた市民に表現活動を提供します。
そして、10月・11月の期間(予定) 成果の発表という形で、展覧会を開催します。
2010年05月06日
臨時休廊
5月6日7日振替休廊とさせていただきます。土曜日より開廊いたします。ただし、笠島地区町並み保存会総会の為、11時-14時までギャラリーは閉じています。変則的な時間となりますが、宜しくお願いいたします。
2010年05月05日
食とアートのプロジェクト
5月2日、食とアートのプロジェクト
アーティスト・イン塩飽本島 『~晴れに耕す。そしてアート~』二次審査を
ギャラリーアルテにて行いました。
食とアートのプロジェクト
アーティスト・イン塩本島 『~晴れに耕す。そしてアート~』二次審査概要
日時 5月2日午後二時より
会場 ギャラリーアルテにて
2つの計画【A食・野菜栽培 + Bアートの展開】によって地域の人々との交流を生み出し、地域の活力
の創造を目的とするプロジェクトです。
「Art Love Food」というテーマに沿った内容の創作を行うアーティストを募集します。
滞在中、地域の文化、環境などからアイディアを得て、創作活動を行い、新たな作品を通じて
『住民への飲食の場づくり』『土産物づくり』に繫がるアクションプランを募集しました。
以下の4名の方がB部門応募アーティストとして、本島へお越しいただきました。
佐藤佳紀 さん(京都)
柴田智明 さん(東京)
松宮硝子 さん(東京)
山田健二 さん(東京)
審査をお願いした方々は、以下の方々
吉川神津夫氏 徳島県立美術館学芸員
平野祐一氏 平野地域計画設計事務所主宰
高島昭夫氏 笠島地区自治会長
梅谷幾代 ギャラリーアルテ+SAW(瀬戸内アートウェーブ)主宰
5時まで、とてもユニークで楽しい審査会となりました。
レジデンス作家として2名が選出されます。
*****************
それにしても皆さん素敵なアーティストでした。全てを今お話できないのですが
記憶に残る出会いばかりでした。
柴田智明さんは、30日から本島入りして、30日は野宿されてたそうです。
1日は、丸亀のまきちゃん宅にお泊りしていただきました。
山田健二さんは、2日面接日に本島入り。でももう一泊して東京へ戻る予定
だったので、2日夜は丸亀まきちゃん宅にお泊りして、3日7時のフェリーで
まきちゃんと一緒に再び本島へやってきてくれました。
松宮硝子さんは、東京から1日夜行バスで丸亀へ、2日終了後、本島ー児島経由で
戻られました。
佐藤佳紀さんは、香川出身。現在京都造形大学生なので、京都ー本島ー香川ー京都
という経路で戻られたのでは?
皆さんひとまず、お疲れ様でした。
そして、選出された2名の方には、7月から2ヶ月の滞在制作をお願い致します。
アーティスト・イン塩飽本島 『~晴れに耕す。そしてアート~』二次審査を
ギャラリーアルテにて行いました。
食とアートのプロジェクト
アーティスト・イン塩本島 『~晴れに耕す。そしてアート~』二次審査概要
日時 5月2日午後二時より
会場 ギャラリーアルテにて
2つの計画【A食・野菜栽培 + Bアートの展開】によって地域の人々との交流を生み出し、地域の活力
の創造を目的とするプロジェクトです。
「Art Love Food」というテーマに沿った内容の創作を行うアーティストを募集します。
滞在中、地域の文化、環境などからアイディアを得て、創作活動を行い、新たな作品を通じて
『住民への飲食の場づくり』『土産物づくり』に繫がるアクションプランを募集しました。
以下の4名の方がB部門応募アーティストとして、本島へお越しいただきました。
佐藤佳紀 さん(京都)
柴田智明 さん(東京)
松宮硝子 さん(東京)
山田健二 さん(東京)
審査をお願いした方々は、以下の方々
吉川神津夫氏 徳島県立美術館学芸員
平野祐一氏 平野地域計画設計事務所主宰
高島昭夫氏 笠島地区自治会長
梅谷幾代 ギャラリーアルテ+SAW(瀬戸内アートウェーブ)主宰
5時まで、とてもユニークで楽しい審査会となりました。
レジデンス作家として2名が選出されます。
*****************
それにしても皆さん素敵なアーティストでした。全てを今お話できないのですが
記憶に残る出会いばかりでした。
柴田智明さんは、30日から本島入りして、30日は野宿されてたそうです。
1日は、丸亀のまきちゃん宅にお泊りしていただきました。
山田健二さんは、2日面接日に本島入り。でももう一泊して東京へ戻る予定
だったので、2日夜は丸亀まきちゃん宅にお泊りして、3日7時のフェリーで
まきちゃんと一緒に再び本島へやってきてくれました。
松宮硝子さんは、東京から1日夜行バスで丸亀へ、2日終了後、本島ー児島経由で
戻られました。
佐藤佳紀さんは、香川出身。現在京都造形大学生なので、京都ー本島ー香川ー京都
という経路で戻られたのでは?
皆さんひとまず、お疲れ様でした。
そして、選出された2名の方には、7月から2ヶ月の滞在制作をお願い致します。
2010年04月29日
連休
連休は5月5日まで休まず開廊します。
27日16時過ぎから本島へ入りました。この日は火曜日なので、溜まったギャラリーの仕事を
済ませておこうと、入ったのですが、「珈琲のませてくれる?」って
すぐ妹尾さんたちに見つかって?・・やっぱり仕事が進みません。
まあ、夜中にやろう・・ということで、あまり進みません(悩み)
翌日28日は、櫻井伸也さん(広島生まれ・現在イタリアトリノ在住)が、
帰国していて、アルテをたずねてくださいました。
彼とはアートフェア東京2010でもお隣のギャラリーから出展していたので、
4月に再会しました。ようこそ本島アルテへ。。
5月1日から金沢で展覧会がはじまるそうです。イタリアと日本で作品を発表されています。
6月ごろイタリアへ帰国予定とか。来年はヴェネチアビエンナーレがあるので、イタリアへ
行きたいです・・・。アートについていろいろ話し合いました。欧州も日本も厳しい状況のようです。
アジアは活気があります。アルテにも 台北、韓国、上海などの
アートフェアのお誘いをいただいていますが、今年は本島が忙しくなるので、参加は無理xですね。
*********
28日、岡さんが 新鮮なイカを6はいも持ってきてくださいました。
でも私は、いきたイカの処理など出来ません。。1はいだけ見本で
処理の仕方を教えてくださいましたが、勇気がなくて、そのままにしていました。
で・・夕方岡さんがお仕事が終わって尋ねてくださるまで櫻井君とワインを飲みつづけながら
雑誌取材の下見の方や丸亀市内の中学生と先生にパスタやランチをお出ししていました。
櫻井さんに手伝ってもらいながら。。
**************
29日は、香川+岡山の合同事業で、瀬戸大橋ウォーキングの人々300人が
いらっしゃっています。3班にわかれて本島を歩くのだそうです。お弁当持参の方なのですが
アルテにも作品鑑賞をかねて、カレーや珈琲を食していただきました。
喜んでくださるのでありがたいです。
春になり、様々な人々が訪れて居ます。
27日16時過ぎから本島へ入りました。この日は火曜日なので、溜まったギャラリーの仕事を
済ませておこうと、入ったのですが、「珈琲のませてくれる?」って
すぐ妹尾さんたちに見つかって?・・やっぱり仕事が進みません。
まあ、夜中にやろう・・ということで、あまり進みません(悩み)
翌日28日は、櫻井伸也さん(広島生まれ・現在イタリアトリノ在住)が、
帰国していて、アルテをたずねてくださいました。
彼とはアートフェア東京2010でもお隣のギャラリーから出展していたので、
4月に再会しました。ようこそ本島アルテへ。。
5月1日から金沢で展覧会がはじまるそうです。イタリアと日本で作品を発表されています。
6月ごろイタリアへ帰国予定とか。来年はヴェネチアビエンナーレがあるので、イタリアへ
行きたいです・・・。アートについていろいろ話し合いました。欧州も日本も厳しい状況のようです。
アジアは活気があります。アルテにも 台北、韓国、上海などの
アートフェアのお誘いをいただいていますが、今年は本島が忙しくなるので、参加は無理xですね。
*********
28日、岡さんが 新鮮なイカを6はいも持ってきてくださいました。
でも私は、いきたイカの処理など出来ません。。1はいだけ見本で
処理の仕方を教えてくださいましたが、勇気がなくて、そのままにしていました。
で・・夕方岡さんがお仕事が終わって尋ねてくださるまで櫻井君とワインを飲みつづけながら
雑誌取材の下見の方や丸亀市内の中学生と先生にパスタやランチをお出ししていました。
櫻井さんに手伝ってもらいながら。。
**************
29日は、香川+岡山の合同事業で、瀬戸大橋ウォーキングの人々300人が
いらっしゃっています。3班にわかれて本島を歩くのだそうです。お弁当持参の方なのですが
アルテにも作品鑑賞をかねて、カレーや珈琲を食していただきました。
喜んでくださるのでありがたいです。
春になり、様々な人々が訪れて居ます。
2010年04月23日
報告 アートフェア東京2010
笠島でまたお年寄りが一人亡くなり、本日は宇多津のベルモニーでお葬式を
するそうです。そのため、島の人はほとんど葬儀に参列するため
フェリーで出かけ、笠島はしーーーーんとしています。
*************
ギャラリーの仕事に専念しています。
ついでに、アートフェア東京の報告をしておきます。
アートフェアは内覧会4月1日。一般公開4月2日-4日まで
毎年、東京丸の内にある東京国際フォーラムで開催されます。
今年は国内外から140画廊が出展し、古美術から現代美術まで
様々な画廊が(扱い作家の)作品を紹介・販売する_国内では
規模が最大のフェアです。アルテは第二回から継続して出展しています。
大阪・京都からの出展はいくつかありますが、四国以西からはアルテのみ。
四国からだと、作品の輸送や期間中の滞在など、出展料に加えて経費が海外のフェアに
出展する感覚で必要になります。海外の場合はさらに、関税も考えなければなりません。
フェアに出展するには、作家との連携や意思の疎通も大切です。大変なものxです。
今年は3月31日から東京へ行き4月5日に戻ってきました。
31日は、リコシェの柳ケ瀬さんが、深川にあるそら庵さん、深川番所さんなどへ
案内してくださいまして、夜は深川ラボの白濱さんご夫妻も加わって、皆さんで
歓迎会というか、ご一緒に会食をしていただきました。
そら庵(1F)と深川番所(2F)は、深川にある古い印刷工場を再利用して活用していました。
イベントスペースやブックカフェ。朗読会、アコースティックライブ、自主映画会、トークイベントなど
のびやかで自由な場を作っていらっしゃいました。
アルテやアートフェアに出展するギャラリーとは、異なって、実にのびやかな印象でした。
アートフェアは昨年よりも初日から来場者は多かったのですが、
全般的に印象にのこるブースがなく、手堅くまとまった印象です。
ただ、来場数は昨年よりも5000人増の5万人とか。
購入するためというよりは、鑑賞のために来ている方が多く、
エンターテイメント化しているといっても良いでしょう。
これが日本のアートマーケットとしてのアートフェアかというもので
観客の態度、印象は大阪のアートフェアに酷似していると感じました。
ギャラリーそのもの、または作品を発表することその方法を
リストラする時期に来ているのだという実感を強くしました。
そういう意味でも本島へ移って良かったと確信を持ちました。
会場では、彦坂尚嘉さんと藏本秀彦さんの作品を持って行きました。
売り上げは良くなかったのですが、観客からの反応はとても良かったです。
他とは違いがあったようで、いい反応をいただきました。
本島や笠島地区にあるギャラリーということもアピール致しました。
確かに、離島に開いている画廊は、唯一でした。興味をもってくださった
方からは、ぜひ行きたいと。。今年は7月ごろ瀬戸内国際芸術祭があるので
香川に行くから、本島へも行きますよ。。
などなど、うきうきしたお声をかけていただきました。
楽しかったですよ。
するそうです。そのため、島の人はほとんど葬儀に参列するため
フェリーで出かけ、笠島はしーーーーんとしています。
*************
ギャラリーの仕事に専念しています。
ついでに、アートフェア東京の報告をしておきます。
アートフェアは内覧会4月1日。一般公開4月2日-4日まで
毎年、東京丸の内にある東京国際フォーラムで開催されます。
今年は国内外から140画廊が出展し、古美術から現代美術まで
様々な画廊が(扱い作家の)作品を紹介・販売する_国内では
規模が最大のフェアです。アルテは第二回から継続して出展しています。
大阪・京都からの出展はいくつかありますが、四国以西からはアルテのみ。
四国からだと、作品の輸送や期間中の滞在など、出展料に加えて経費が海外のフェアに
出展する感覚で必要になります。海外の場合はさらに、関税も考えなければなりません。
フェアに出展するには、作家との連携や意思の疎通も大切です。大変なものxです。
今年は3月31日から東京へ行き4月5日に戻ってきました。
31日は、リコシェの柳ケ瀬さんが、深川にあるそら庵さん、深川番所さんなどへ
案内してくださいまして、夜は深川ラボの白濱さんご夫妻も加わって、皆さんで
歓迎会というか、ご一緒に会食をしていただきました。
そら庵(1F)と深川番所(2F)は、深川にある古い印刷工場を再利用して活用していました。
イベントスペースやブックカフェ。朗読会、アコースティックライブ、自主映画会、トークイベントなど
のびやかで自由な場を作っていらっしゃいました。
アルテやアートフェアに出展するギャラリーとは、異なって、実にのびやかな印象でした。
アートフェアは昨年よりも初日から来場者は多かったのですが、
全般的に印象にのこるブースがなく、手堅くまとまった印象です。
ただ、来場数は昨年よりも5000人増の5万人とか。
購入するためというよりは、鑑賞のために来ている方が多く、
エンターテイメント化しているといっても良いでしょう。
これが日本のアートマーケットとしてのアートフェアかというもので
観客の態度、印象は大阪のアートフェアに酷似していると感じました。
ギャラリーそのもの、または作品を発表することその方法を
リストラする時期に来ているのだという実感を強くしました。
そういう意味でも本島へ移って良かったと確信を持ちました。
会場では、彦坂尚嘉さんと藏本秀彦さんの作品を持って行きました。
売り上げは良くなかったのですが、観客からの反応はとても良かったです。
他とは違いがあったようで、いい反応をいただきました。
本島や笠島地区にあるギャラリーということもアピール致しました。
確かに、離島に開いている画廊は、唯一でした。興味をもってくださった
方からは、ぜひ行きたいと。。今年は7月ごろ瀬戸内国際芸術祭があるので
香川に行くから、本島へも行きますよ。。
などなど、うきうきしたお声をかけていただきました。
楽しかったですよ。