 › gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › 2009年10月
› gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › 2009年10月2009年10月23日
【保存地区の概要】
丸亀市文化課より
笠島の町並みについての資料をいただきました。
特異な特徴がよくまとめられているので
皆さんにもご紹介したいので、ご覧ください。
『丸亀市塩飽本島町笠島伝統的建造物群保存地区保存計画のあらまし』より
【保存地区の概要】
沿革
笠島は、瀬戸内海の南北を扼す塩飽諸島も中心島である本島の東端に位置する。ここは瀬戸内海交通の要衝であり、古来塩飽水軍の最重要拠点としての地位を占めていた。
笠島には、城根・中之浦・新在家・山根・屋釜の5集落を有し、城根・中之浦は家並み続きであるものの、新在家・山根・屋釜は山越えで離れている。保存地区はその中心集落である。笠島といえば、一般にこの山根地区を指す。
建永2年(1207)法然上人が配流の途次に一時身を寄せた、地頭駿河権守保遠入道西忍の館は、この笠島の城山にあったし、16世紀後半に亡ぼされた代官福田又次郎は城山に居城していた。 塩飽の水軍は、天正5年(1577)信長より触掛りの特権を得、同18年(1590)秀吉は塩飽領1250石を船方650人に与え、家康もこれにならい、以来幕末まで、他に例を見ない いわゆる「人名」 による自治が行われていた。
江戸初期には、幕府御用船・水主役を勤め、全国的な海上輸送を一手に引き受け、多くの船持衆が生まれ、豊かな漁場による漁猟海上がこれを補って、塩飽の最盛期を迎えている。この頃、笠島は塩飽諸島中で最良の港 (停泊地、修理場) であった。
しかし、元禄頃(17世紀末)から全国的に廻船業が成長するにつれ、塩飽の海運業は衰退の一途をたどり、18世紀中頃には、他国へ出稼ぎに行かざるを得ない経済状態に陥り、笠島の港としての機能は与島に奪われてしまった。
出稼ぎは、これまでに培われてきた航海技術・造船技術の優秀さから、加古稼・大工稼が主で、 「人名」 はほとんど漁猟働はしなかった。こうして、中国地方を中心に名を高めた塩飽大工が発生し、各地で活躍し始めることになり、時代が降るにつれてその傾向は増大する。
【現況】
出稼ぎは戦後も続き、島に土地・建物を残しながら島外に居住して他の職につく者が増加する。こうした人口流出は近年ようやく停滞したものの、大半が老人世帯となり、また空家の多い過疎地と化している。港は昭和初期に始まる埋め立て、護岸工事により、旧状の一部を残しながら漁港として改修され (ただし漁家は港の西に続く中之浦に集中する ) 、
またこの港に通じる道路が城山の海岸沿いに設けられるなど、景観は変貌しつつある。しかし、集落内においては、新しい形式の建物は散在的にみられるにすぎず、江戸後期以後の伝統的形式の家屋からなる集落景観をよく止めている。
このような状況に対し、昭和55年に、笠島の住民を中心にした保存協力会が発足し、丸亀市の補助のもとで、主として傷みの激しい屋根の補修工事を行って、景観の維持に努めてきている。
【集落構成とその特性】
歴史的地理的な条件は、塩飽の集落に、他地方の漁村集落、港町集落等とはひときわ異なる構成をとらせることになる。
中でも笠島は、組織的で計画的な構成が取られている。現在に続く集落構成の成立時期については詳らかでないが、正保4年(1647)には現在と同規模を有し、既に分村の新在家が存在しているので、その形式は少なくとも塩飽が最盛期を迎えた近世初期には遡るであろう。あるいは、城山の居城跡と集落構成との関係が現在では希薄であるものの、集落は港に表を向けるよりは、山手つまり旧地頭館の一郭の跡と伝える専称寺、あるいは代官福田氏の居城跡 (土塁・空堀を残す) の方向を表にしている点は、集落構成の基本が、居城のあった中世期に遡るのを物語るのかもしれない。
集落は、北が海に面して港を擁し、他の三方は山で囲まれた東西約200M、南北約 200Mを占める
東は居城のあった城山で、他の二方の山麓には、法然上人ゆかりの専称寺の他、真言宗4か寺 (現在は廃寺) が集落を取り囲み、城山と相対する西の山麓には産土神を祀る尾上神社があり、集落の東西両端とほぼ中央に恵比寿神を祀り、港の東端には常夜燈を設け、港の中には、「たで場」があった。
道路は、東の城山と北の光厳寺山の境に向かって南北を通る東小路、海岸線に平行して弓なりに曲がる東西道路のマッチョ通りを主道路とし、東西道路は両端で枡形となり、櫛状に海岸に向かって枝道が設けられる。西端にも山に向かって尾上神社前を通る南北道路があり、南の山に沿う東西道路の田中小路で東小路と結ばれる。これらの道路は湾曲し、T字型、食い違い十字型に交わり、一部の道幅を変え、見通しできぬような組織的構成が取られている。江戸時代には、東小路、マッチョ通り、田中小路がともに「町通り」と称され、田中小路のほぼ中央南側に、年寄の一人であった吉田家があった。
また、港よりの主入口を示すような道路形態はみられず、港を裏とする宅地割がほどこされていて、集落入り口は、港とは逆の東小路mの南端となる等の特性を見せる。
この集落入り口横には、法然上人ゆかりの専称寺があり、また「人名」の墓碑(寛永4年・1627・銘の吉田彦左衛門の墓碑は、国指定史跡)があって、村への出入りの度に拝したという。なお、城山の東海岸を廻る道路は新設(県道)である。
【伝統的建造物群の特性】
現在は、山麓に並んでいた4カ寺は廃寺となり、港は埋め立て、護岸工事によって形状を変え(ただし、防波堤の一部は旧位置に残る)、過疎化による建物倒壊は家並みに歯抜けを生じ、また一部に新形式の家が見られるものの、いまなお往時の面影を色濃く残し、江戸時代の道路空間や建物の造形がよくわかる。
東小路、マッチョ通りの主要道路沿いには、江戸時代から大正期にかけて建てられた切妻造・片入母屋造・入母屋造本瓦葺平入形式のツシ二階造りで、上階を塗屋造とし、虫籠窓・格子窓を設け、下階は、腰格子付雨戸構えと、出格子・窓出格子を組み合わせた表構えとする町屋形式の建物が立ち並び、間に土塀構えの家が散在する。
特に、アイストップを形成する家では、一部になまこ壁を設けて引き立たせるなど、すぐれた景観美を造り出している。一方、主道路から離れると長屋門構えの家が建ち、主道路とは異なった道路空間が出現する。
塩飽の 他集落では、長屋門を持つ家屋で道路空間を形成するのが原則で、笠島に属する新在家ではこの構成を取っている。
笠島のような構成は。塩飽で笠島とともに最重要集落であった泊に見出せるが、泊では笠島ほど組織的ではない。
また港を有し、あるいは海に面する集落では、海に面して長屋門が立ち並ぶ構成が取られているのに、笠島では、港側に家屋の背面を見せていて、こうした点にも笠島の特性がある。
なお、東小路の西側建物前には石積みの排水路が海まで通じ、各家ごとに石を渡し、東小路とマッチョ通りの交差部では、石橋が掛け渡されていた。排水路は、一部にコンクリートによる補修が施され、また蓋が被せられているところもあるが、こうした排水路も道路空間の質をたかめている。特に主道路沿いの建物の地形石は、その周辺部より一段と丁寧な仕事が施されている。
【保存整備の基本方針】
道路からの建築物の景観のみならず、その背景となる山容、さらには、城山並びに尾上神社境内から集落が一目されることを考慮の上、伝統的景観を失しないよう修理・修景・復旧につとめ、空間他の整備活用をはかるとともに文化施設等を設けるなど、住民の生活向上をはかるような整備計画を進める。
笠島の町並みについての資料をいただきました。
特異な特徴がよくまとめられているので
皆さんにもご紹介したいので、ご覧ください。
『丸亀市塩飽本島町笠島伝統的建造物群保存地区保存計画のあらまし』より
【保存地区の概要】
沿革
笠島は、瀬戸内海の南北を扼す塩飽諸島も中心島である本島の東端に位置する。ここは瀬戸内海交通の要衝であり、古来塩飽水軍の最重要拠点としての地位を占めていた。
笠島には、城根・中之浦・新在家・山根・屋釜の5集落を有し、城根・中之浦は家並み続きであるものの、新在家・山根・屋釜は山越えで離れている。保存地区はその中心集落である。笠島といえば、一般にこの山根地区を指す。
建永2年(1207)法然上人が配流の途次に一時身を寄せた、地頭駿河権守保遠入道西忍の館は、この笠島の城山にあったし、16世紀後半に亡ぼされた代官福田又次郎は城山に居城していた。 塩飽の水軍は、天正5年(1577)信長より触掛りの特権を得、同18年(1590)秀吉は塩飽領1250石を船方650人に与え、家康もこれにならい、以来幕末まで、他に例を見ない いわゆる「人名」 による自治が行われていた。
江戸初期には、幕府御用船・水主役を勤め、全国的な海上輸送を一手に引き受け、多くの船持衆が生まれ、豊かな漁場による漁猟海上がこれを補って、塩飽の最盛期を迎えている。この頃、笠島は塩飽諸島中で最良の港 (停泊地、修理場) であった。
しかし、元禄頃(17世紀末)から全国的に廻船業が成長するにつれ、塩飽の海運業は衰退の一途をたどり、18世紀中頃には、他国へ出稼ぎに行かざるを得ない経済状態に陥り、笠島の港としての機能は与島に奪われてしまった。
出稼ぎは、これまでに培われてきた航海技術・造船技術の優秀さから、加古稼・大工稼が主で、 「人名」 はほとんど漁猟働はしなかった。こうして、中国地方を中心に名を高めた塩飽大工が発生し、各地で活躍し始めることになり、時代が降るにつれてその傾向は増大する。
【現況】
出稼ぎは戦後も続き、島に土地・建物を残しながら島外に居住して他の職につく者が増加する。こうした人口流出は近年ようやく停滞したものの、大半が老人世帯となり、また空家の多い過疎地と化している。港は昭和初期に始まる埋め立て、護岸工事により、旧状の一部を残しながら漁港として改修され (ただし漁家は港の西に続く中之浦に集中する ) 、
またこの港に通じる道路が城山の海岸沿いに設けられるなど、景観は変貌しつつある。しかし、集落内においては、新しい形式の建物は散在的にみられるにすぎず、江戸後期以後の伝統的形式の家屋からなる集落景観をよく止めている。
このような状況に対し、昭和55年に、笠島の住民を中心にした保存協力会が発足し、丸亀市の補助のもとで、主として傷みの激しい屋根の補修工事を行って、景観の維持に努めてきている。
【集落構成とその特性】
歴史的地理的な条件は、塩飽の集落に、他地方の漁村集落、港町集落等とはひときわ異なる構成をとらせることになる。
中でも笠島は、組織的で計画的な構成が取られている。現在に続く集落構成の成立時期については詳らかでないが、正保4年(1647)には現在と同規模を有し、既に分村の新在家が存在しているので、その形式は少なくとも塩飽が最盛期を迎えた近世初期には遡るであろう。あるいは、城山の居城跡と集落構成との関係が現在では希薄であるものの、集落は港に表を向けるよりは、山手つまり旧地頭館の一郭の跡と伝える専称寺、あるいは代官福田氏の居城跡 (土塁・空堀を残す) の方向を表にしている点は、集落構成の基本が、居城のあった中世期に遡るのを物語るのかもしれない。
集落は、北が海に面して港を擁し、他の三方は山で囲まれた東西約200M、南北約 200Mを占める
東は居城のあった城山で、他の二方の山麓には、法然上人ゆかりの専称寺の他、真言宗4か寺 (現在は廃寺) が集落を取り囲み、城山と相対する西の山麓には産土神を祀る尾上神社があり、集落の東西両端とほぼ中央に恵比寿神を祀り、港の東端には常夜燈を設け、港の中には、「たで場」があった。
道路は、東の城山と北の光厳寺山の境に向かって南北を通る東小路、海岸線に平行して弓なりに曲がる東西道路のマッチョ通りを主道路とし、東西道路は両端で枡形となり、櫛状に海岸に向かって枝道が設けられる。西端にも山に向かって尾上神社前を通る南北道路があり、南の山に沿う東西道路の田中小路で東小路と結ばれる。これらの道路は湾曲し、T字型、食い違い十字型に交わり、一部の道幅を変え、見通しできぬような組織的構成が取られている。江戸時代には、東小路、マッチョ通り、田中小路がともに「町通り」と称され、田中小路のほぼ中央南側に、年寄の一人であった吉田家があった。
また、港よりの主入口を示すような道路形態はみられず、港を裏とする宅地割がほどこされていて、集落入り口は、港とは逆の東小路mの南端となる等の特性を見せる。
この集落入り口横には、法然上人ゆかりの専称寺があり、また「人名」の墓碑(寛永4年・1627・銘の吉田彦左衛門の墓碑は、国指定史跡)があって、村への出入りの度に拝したという。なお、城山の東海岸を廻る道路は新設(県道)である。
【伝統的建造物群の特性】
現在は、山麓に並んでいた4カ寺は廃寺となり、港は埋め立て、護岸工事によって形状を変え(ただし、防波堤の一部は旧位置に残る)、過疎化による建物倒壊は家並みに歯抜けを生じ、また一部に新形式の家が見られるものの、いまなお往時の面影を色濃く残し、江戸時代の道路空間や建物の造形がよくわかる。
東小路、マッチョ通りの主要道路沿いには、江戸時代から大正期にかけて建てられた切妻造・片入母屋造・入母屋造本瓦葺平入形式のツシ二階造りで、上階を塗屋造とし、虫籠窓・格子窓を設け、下階は、腰格子付雨戸構えと、出格子・窓出格子を組み合わせた表構えとする町屋形式の建物が立ち並び、間に土塀構えの家が散在する。
特に、アイストップを形成する家では、一部になまこ壁を設けて引き立たせるなど、すぐれた景観美を造り出している。一方、主道路から離れると長屋門構えの家が建ち、主道路とは異なった道路空間が出現する。
塩飽の 他集落では、長屋門を持つ家屋で道路空間を形成するのが原則で、笠島に属する新在家ではこの構成を取っている。
笠島のような構成は。塩飽で笠島とともに最重要集落であった泊に見出せるが、泊では笠島ほど組織的ではない。
また港を有し、あるいは海に面する集落では、海に面して長屋門が立ち並ぶ構成が取られているのに、笠島では、港側に家屋の背面を見せていて、こうした点にも笠島の特性がある。
なお、東小路の西側建物前には石積みの排水路が海まで通じ、各家ごとに石を渡し、東小路とマッチョ通りの交差部では、石橋が掛け渡されていた。排水路は、一部にコンクリートによる補修が施され、また蓋が被せられているところもあるが、こうした排水路も道路空間の質をたかめている。特に主道路沿いの建物の地形石は、その周辺部より一段と丁寧な仕事が施されている。
【保存整備の基本方針】
道路からの建築物の景観のみならず、その背景となる山容、さらには、城山並びに尾上神社境内から集落が一目されることを考慮の上、伝統的景観を失しないよう修理・修景・復旧につとめ、空間他の整備活用をはかるとともに文化施設等を設けるなど、住民の生活向上をはかるような整備計画を進める。
2009年10月19日
障子の張替え
明日は7:40分発のフェリーにのって
本島へ行きます。
NTTが電話線の工事を行うので、立会いと
昨日洗った障子を張り替えるためです。
丸亀市の文化課の方も伝建地区なので
屋根の修理の検討のために来てくださいます。
なんとか31日搬入に間に合うように
大移動完了しなければなりません。
それにしても昨日も快晴で気持ちが良かったです。
寒くなってきましたが、島は少し陸地よりも温度が高いとか
野菜も早生で出来るそうです。
野菜作りは来年からです。
機能はJAの方が島のお年寄りに野菜の苗を届けていました。
アルテに来てくださった女性が、ハーブの苗を下さるとのこと。
先日チバちゃんから、もらったアーティークチョークの苗にせっせと水遣りをしています。
少し大きくなったような気がします。
なんだか楽しみ。。
それにしても、ご飯ご飯と島のお年寄りは待ちわびて下さっています。
いま何ができるか考え中。
火曜日から日曜日までの開店で手伝ってくださるかた求めています。
本島へ行きます。
NTTが電話線の工事を行うので、立会いと
昨日洗った障子を張り替えるためです。
丸亀市の文化課の方も伝建地区なので
屋根の修理の検討のために来てくださいます。
なんとか31日搬入に間に合うように
大移動完了しなければなりません。
それにしても昨日も快晴で気持ちが良かったです。
寒くなってきましたが、島は少し陸地よりも温度が高いとか
野菜も早生で出来るそうです。
野菜作りは来年からです。
機能はJAの方が島のお年寄りに野菜の苗を届けていました。
アルテに来てくださった女性が、ハーブの苗を下さるとのこと。
先日チバちゃんから、もらったアーティークチョークの苗にせっせと水遣りをしています。
少し大きくなったような気がします。
なんだか楽しみ。。
それにしても、ご飯ご飯と島のお年寄りは待ちわびて下さっています。
いま何ができるか考え中。
火曜日から日曜日までの開店で手伝ってくださるかた求めています。
2009年10月16日
屋号あたらしや

フェリー乗り場は丸亀駅から北へ徒歩10分

港の詳細地図
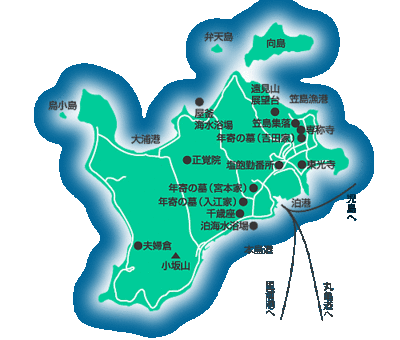
フェリーで35分
高速艇なら20分
徒歩で港から笠島地区へはいると
こんな感じ





門をはいると



水周りは全て増改築されていル。

庭


2009年10月14日
本日も島日和
10:40分発のフェリーが、ワイヤトラブルのため、臨時便 高速艇でした。
高速艇は、早足なので(20分)あっという間に泊港に到着します。
私が9:30にギャラリーに来ていなかったので
お外の姑・しゅうとめ(まきちゃん・遠山さん)は、プンプンとお怒り気味。
すんません。と愛嬌をこめた笑顔で返して笠島地区への道行き。
でも帰りはみんな いいところやなぁ~。
今度来るときは釣竿もってこよう。。
と海幸彦 山幸彦 に変身しておりました。

明日は蔵本秀彦さんと本島へ行きます。
11月からの個展の確認のため。
本島の住所と電話番号です。
御用がある場合は、11月からはこちらにご連絡ください。
763-0221
香川県丸亀市本島町笠島328番地(屋号あたらしや)
℡ 0877-57-8255 (ハニゴゴー)と覚えてください。
営業日・時間はまだ決めかねています。
いろいろ試験的に行って、微調整ですね。
看板は gallery ARTE+SAW(瀬戸内アートウェーブ)という表記になりそうです。
ではまた
2009年10月13日
本島清掃
11日.12日 本島笠島地区のgallery ARTE+SAWが使用する清掃の第一回清掃を
行いました。10:40分のフェリーで本島到着。
徒歩で15分の道のりを掃除機やその夜の食材を持って汗をかきながら運びました。
快晴で涼しくとてもいい道中でした。
笠島地区に入ると、目的の建物の前で男性が庭木の剪定中。
自治会長である高島さんが既に庭木の剪定をしてくださっていました。
先発隊はチバちゃんと私の二人。
・・女の子二人では庭木は無理じゃろうから
こっちはやるから、はよ中の方を掃除せいや。。
とうれしい頼もしいお言葉をかけていただき、私たちは8畳.8畳.6畳の和室
12畳の台所・お風呂場洗面所の床、増改改築された
掃除機をかけ雑巾かけ。20年来の土ぼこり、数回噴いてもバケツの水は真っ黒ですぅ。
これも修行と黙々と。。
やがて天理教へ行っていたまきちゃんが到着。
まきちゃんは、私にとっては姑のようなものですね。
なにかと、やり方にこだわりが。あって、五月の蝿のよう。。
まあ、なんやかんやで、日も暮れて
民宿に高島さんをお招きしてキムチ鍋を囲んで様々お話を伺いました。
高島さんは、息子さんは二人いらっしゃるそうですが、
現在アルツハイマーの病を患っている長年連れ添った奥さんをご自身で介護されています。
女子を持ったことがなかったから、女の子はやさしくていいと、うれしそうに話していらっしゃいました。
「とにかく若い人にきてもらいたい。」
「無理をせんでいいから、でもいつも開いていて欲しい」と伺って、
いろいろ託していただいて、なんとか期待を裏切らないように応えて行きたいと思いました。
島の人々がいれかわり、訪ねてくださって・・。
楽しみに待っていてくださることを感じて、
前日まで、意思挿通の欠ける、ちょっとめんどくさい人とやりとりに疲れていたので
久々にほっこりした気もちになれました。
翌日もまた清掃。平野さんがおにぎりを大量につくってきてくれました。
アメリカから平野さんのところにステイしているアダム君も一生懸命
荷物を蔵に運んだり、屋根裏のお掃除してくださいました。
今日は一休みして
明日14日 再び島へ行きます。
明日は、電気に詳しい豊田さん、遠山さん
加地さんもきてくださるそうです。
栗生さんもフェリーに間に合いそうなら連絡するとのこと
約6名でまた本島へ行くことになりました。
ひとまず
ご報告
行いました。10:40分のフェリーで本島到着。
徒歩で15分の道のりを掃除機やその夜の食材を持って汗をかきながら運びました。
快晴で涼しくとてもいい道中でした。
笠島地区に入ると、目的の建物の前で男性が庭木の剪定中。
自治会長である高島さんが既に庭木の剪定をしてくださっていました。
先発隊はチバちゃんと私の二人。
・・女の子二人では庭木は無理じゃろうから
こっちはやるから、はよ中の方を掃除せいや。。
とうれしい頼もしいお言葉をかけていただき、私たちは8畳.8畳.6畳の和室
12畳の台所・お風呂場洗面所の床、増改改築された
掃除機をかけ雑巾かけ。20年来の土ぼこり、数回噴いてもバケツの水は真っ黒ですぅ。
これも修行と黙々と。。
やがて天理教へ行っていたまきちゃんが到着。
まきちゃんは、私にとっては姑のようなものですね。
なにかと、やり方にこだわりが。あって、五月の蝿のよう。。
まあ、なんやかんやで、日も暮れて
民宿に高島さんをお招きしてキムチ鍋を囲んで様々お話を伺いました。
高島さんは、息子さんは二人いらっしゃるそうですが、
現在アルツハイマーの病を患っている長年連れ添った奥さんをご自身で介護されています。
女子を持ったことがなかったから、女の子はやさしくていいと、うれしそうに話していらっしゃいました。
「とにかく若い人にきてもらいたい。」
「無理をせんでいいから、でもいつも開いていて欲しい」と伺って、
いろいろ託していただいて、なんとか期待を裏切らないように応えて行きたいと思いました。
島の人々がいれかわり、訪ねてくださって・・。
楽しみに待っていてくださることを感じて、
前日まで、意思挿通の欠ける、ちょっとめんどくさい人とやりとりに疲れていたので
久々にほっこりした気もちになれました。
翌日もまた清掃。平野さんがおにぎりを大量につくってきてくれました。
アメリカから平野さんのところにステイしているアダム君も一生懸命
荷物を蔵に運んだり、屋根裏のお掃除してくださいました。
今日は一休みして
明日14日 再び島へ行きます。
明日は、電気に詳しい豊田さん、遠山さん
加地さんもきてくださるそうです。
栗生さんもフェリーに間に合いそうなら連絡するとのこと
約6名でまた本島へ行くことになりました。
ひとまず
ご報告
2009年10月06日
地域の方でにぎわう会場

丸亀港天昌丸(とんぺい提供).

踏切南側ガレリア西竹.
さすが、地元提供の写真を素材にしているだけあって、
地元の来廊が続いています。
家の家がある。とか
みっちゃんこないだ来で!元気にしとる・・とか
浜町アルテでの最後の展覧会は、これまでとはガラッと観客が異なったものになっています。
さりげなく本島へ移転することも伝えると
また本島の話で盛り上がって。
本島へ行きますよ。とフェリー乗り場や運賃、民宿の話で
盛り上がる。
11月からは本島笠島地区 屋号あたらしや のSAW+gallery ARTEで
お待ち申し上げます。
2009年10月05日
嘘の公共性
気持ちよく装うこと
気持ちよく食べること
これは基本的な人間にとっての要素だと思う。
では、「弱い人を助けましょう」と語られるような形で関与する行為が普遍的なことであるか?
違うと感じるのです。
日本は、古くから政治的・社会的・文化的そして経済的にも二重構造を本質にする社会です。
日本の二重構造の原型をもっとも色濃く留めているもの
・・・日本の芸能から考えてみます。
正月になれば各地の民家の門づけ芸の太夫・才蔵
田楽・神楽などの能でいうワキとシテの一対
これは文化的優位者としての外来の神と
劣位者としての田舎の神の、圧服と和睦の交じり合った
「からみ」を原型としています。
さらには、年の始まりには、異界から福をもたらすとして、歓迎される門付け芸の人々は
一年を差別の中で暮らしていたのです。
日本の言語芸術は宴会の娯楽を起源としているものが多く見受けられます。
田舎の神社のお神楽の踊りをみると、興味深いことがわかります。
まず、宴会の主役は主だったお客さんです。その主だったお客さんは家の訪問客であるだけでなく
この地方への新米の客でもあります。
このお客への相方として地方の精霊が出てきて、主役のしぐさや話す言葉を
とぼけた仕方でまねをし、そのまね事のとぼけ加減を通して、田舎神は主役の言いつけに
抗い、また背いたりします。
そのうえで、結局は田舎神の降伏で終わります。
地方神は、しまいには黙ってしまい、地方神のしかめっ面で終わります。
この芸能の形が出来たのは、古代の列島に「中央政府がつくられた時代」ということです。
圧倒的な文化の波をうけるこのような場所では、この文化をよく吸収し、
それをより効率的に使いこなせる人間が力を持ち、
それに通じない人間は劣位に置かれてきました。
主神と地方神の対峙の特徴は、面と向かっての対立や反抗がないことです。
優劣二者が、対立しながらもそれが明示されない緊張した関係の原型が
中央から地方にやってきた官僚と地方(じかた)の人間関係という見立てです。
「べしみ」という面があります。口角に力をいれて両唇を強く結んだ異形面です。
オレは絶対にしゃべらないぞ!とおいう渋い感情といくぶんかの不満がこもった表情の面です。
田舎神の「べしみ」という姿勢が本質的にもつ
「一切新しい神の威力にとりあわない」という、いわば無力な抵抗。
古代の芸能のなかに見出せる、圧倒的な征服にたいする記憶は
敗戦時の前面屈服に似た経験ではないかと思うのです。
芸能が受け継がれることで、二重構造の社会を受け入れてきたとしたら、
ほとんどの地域でこのような芸能そのものが崩壊している中で、べしみは
どうなっているのでしょうか?
べしみがなぜ「沈黙」なのか
言葉を持たないのではありません。
劣位である「土着の文化」にも、地方の言葉があり、考え方があり、論理はあるのです。
地方の精霊は、すなわちスピリットは、これが口を開けば、直ちに神語に圧せられて、
たちまち服従を誓う詔を陳べなければならない。
これは、これまで自分のもっていた言葉を失う、奪われる経験だということになります。
古事記にアメノウズメノミコトが海の生き物を集めて、仕えまつるや(私に従うか)と
訪ねるのですが、全ての魚がはい「仕えまつらむ」と復唱する中で
ナマコだけが応えません。
ナマコに「この口はこたえない口だな」といってひもがたなを取り出して
あっという間にその口を割いたという記述があります。
神の言葉は奪う力でもあり、口を開かせる力でもあったのです。
この圧倒的な力に抵抗する最後のすべは、取り合わないということだったのです。
地域と関るアートプロジェクトのすべてとはいいませんが、
その多くはナマコの口をひもがたなで割いていることになっていないでしょうか。
アーレントの言葉に、公共空間とはテーブルのある世界とあります。
テーブルが現れ、人々を分離させつつ結合させる。
なぜテーブルを設えると、そこに人が集まってくるのか。
アーレントはその力を人々がそこに参加しようという「決意」だといいます。
この力の源泉は「公共性」というものでなく「私利私欲」なのだと思います。
それでいいのです。始まりはそいれぞれのもつ私の欲望だと思います。
動機づけでもいいでしょう。人間の本性を自分の「それ以上基礎づけられない」ヒトとしての起点へ復帰することではないかと
感じているのです。
本島という場所に開くテーブルはそういう意図を持っているものなのです。
気持ちよく食べること
これは基本的な人間にとっての要素だと思う。
では、「弱い人を助けましょう」と語られるような形で関与する行為が普遍的なことであるか?
違うと感じるのです。
日本は、古くから政治的・社会的・文化的そして経済的にも二重構造を本質にする社会です。
日本の二重構造の原型をもっとも色濃く留めているもの
・・・日本の芸能から考えてみます。
正月になれば各地の民家の門づけ芸の太夫・才蔵
田楽・神楽などの能でいうワキとシテの一対
これは文化的優位者としての外来の神と
劣位者としての田舎の神の、圧服と和睦の交じり合った
「からみ」を原型としています。
さらには、年の始まりには、異界から福をもたらすとして、歓迎される門付け芸の人々は
一年を差別の中で暮らしていたのです。
日本の言語芸術は宴会の娯楽を起源としているものが多く見受けられます。
田舎の神社のお神楽の踊りをみると、興味深いことがわかります。
まず、宴会の主役は主だったお客さんです。その主だったお客さんは家の訪問客であるだけでなく
この地方への新米の客でもあります。
このお客への相方として地方の精霊が出てきて、主役のしぐさや話す言葉を
とぼけた仕方でまねをし、そのまね事のとぼけ加減を通して、田舎神は主役の言いつけに
抗い、また背いたりします。
そのうえで、結局は田舎神の降伏で終わります。
地方神は、しまいには黙ってしまい、地方神のしかめっ面で終わります。
この芸能の形が出来たのは、古代の列島に「中央政府がつくられた時代」ということです。
圧倒的な文化の波をうけるこのような場所では、この文化をよく吸収し、
それをより効率的に使いこなせる人間が力を持ち、
それに通じない人間は劣位に置かれてきました。
主神と地方神の対峙の特徴は、面と向かっての対立や反抗がないことです。
優劣二者が、対立しながらもそれが明示されない緊張した関係の原型が
中央から地方にやってきた官僚と地方(じかた)の人間関係という見立てです。
「べしみ」という面があります。口角に力をいれて両唇を強く結んだ異形面です。
オレは絶対にしゃべらないぞ!とおいう渋い感情といくぶんかの不満がこもった表情の面です。
田舎神の「べしみ」という姿勢が本質的にもつ
「一切新しい神の威力にとりあわない」という、いわば無力な抵抗。
古代の芸能のなかに見出せる、圧倒的な征服にたいする記憶は
敗戦時の前面屈服に似た経験ではないかと思うのです。
芸能が受け継がれることで、二重構造の社会を受け入れてきたとしたら、
ほとんどの地域でこのような芸能そのものが崩壊している中で、べしみは
どうなっているのでしょうか?
べしみがなぜ「沈黙」なのか
言葉を持たないのではありません。
劣位である「土着の文化」にも、地方の言葉があり、考え方があり、論理はあるのです。
地方の精霊は、すなわちスピリットは、これが口を開けば、直ちに神語に圧せられて、
たちまち服従を誓う詔を陳べなければならない。
これは、これまで自分のもっていた言葉を失う、奪われる経験だということになります。
古事記にアメノウズメノミコトが海の生き物を集めて、仕えまつるや(私に従うか)と
訪ねるのですが、全ての魚がはい「仕えまつらむ」と復唱する中で
ナマコだけが応えません。
ナマコに「この口はこたえない口だな」といってひもがたなを取り出して
あっという間にその口を割いたという記述があります。
神の言葉は奪う力でもあり、口を開かせる力でもあったのです。
この圧倒的な力に抵抗する最後のすべは、取り合わないということだったのです。
地域と関るアートプロジェクトのすべてとはいいませんが、
その多くはナマコの口をひもがたなで割いていることになっていないでしょうか。
アーレントの言葉に、公共空間とはテーブルのある世界とあります。
テーブルが現れ、人々を分離させつつ結合させる。
なぜテーブルを設えると、そこに人が集まってくるのか。
アーレントはその力を人々がそこに参加しようという「決意」だといいます。
この力の源泉は「公共性」というものでなく「私利私欲」なのだと思います。
それでいいのです。始まりはそいれぞれのもつ私の欲望だと思います。
動機づけでもいいでしょう。人間の本性を自分の「それ以上基礎づけられない」ヒトとしての起点へ復帰することではないかと
感じているのです。
本島という場所に開くテーブルはそういう意図を持っているものなのです。
2009年10月03日
復元フォトモ 丸亀あらたし文化商店街 展 はじまりました




猪熊現代美術館地域連携プログラム 『 復元フォトモ 丸亀あらたし文化商店街 』
会場 ギャラリーアルテ・西金・石川タバコ店
10月3日-10月31日
会場 本島町笠島地区 国の重要伝統的建造物群 あたらしや
11月1日-11月24日
11月23日 本島笠島ふれあい祭
会期によって会場が異なりますので、ご注意ください。



