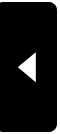2009年05月27日
アーティスト・イン笠島~記憶の集積を創造の海へ
書籍では第四部にはいる池田剛介(孔介)氏による美術批評です。
『これはサイトスペシフィックではない』
2006年十一月二十三日、私は丸亀からのフェリーに揺られ、本島という瀬戸内の小さな島を訪れました。島内の笠島地区でのアーティスト・イン・レジデンス成果発表会場へ向かう道すがら、私の頭にはすでに、「場所」とは何か、サイトスペシフィックとは何か、という問題が据えられていました。 作家がある「地域」へ出向き、「アーティスト・イン・レジデンス」しつつ、「ワークショップ」も催す、とこれだけの語が並べられれば誰でも、 少なくとも現代美術に関わっている人間にとっては誰でも、上のような問題を真っ先に思いつくことになります。ただ、そこに何らかの違和感がなかった訳ではなく、とりわけ福永信という名は、私の考える限り、サイトスペシフィックなる言葉——場の固有性と向かい合い、その特殊性を強調する、その語と容易に結びつくような対象ではありませんでした。
「笠島日記」、それを福永の作品として私が接した際、やはり同様の違和を感じざるを得ませんでした。私はこれまで、ある一定の関心を持って福永の小説に触れてきており、そのいくつかは別の場所で論じてもいます 。作家本人からは「事実として起こった事は小説に書かない」という事をよく聞いている、とすれば、ますますこのテクストは小説から遠ざかるように思えるでしょう。 にも関わらず、インターネット上に公開されていった日記は、単なる活動のルポタージュの枠を超え、彼の小説のあり方をも逆照射しているようにすら思えるのです。端的に言って、「笠島日記」は福永信のこれまでのテクストと決定的に違っています。この違いを見据えること、いわば前者と後者との視差を基に「アーティスト・イン・笠島」プロジェクトの意義を捉えること、これこそが本論の中で目指されています。
■ 鏡としての小説
通常の小説は、最良の作品に限られるであろうが、その作品を通じて外界をヴィヴィッドに映します。作家の感性を媒介として見られた世界が、紋切り型のイメージに回収される事なく生き生きと描写される時、読者は文字どおり本を「通じて」その構築された外界と接する事となります。このような特性は、少なくとも現代の表現としては、文学というメディウムに顕著なものだといえるでしょう。他の多くのメディア、例えば美術においては、20世紀を経て徹底した抽象化が進められてきており、外界を写し取る媒体としての特性は失ってゆきました。対して、文学は言葉を表現の手段として用いている限り、美術でいうような意味での抽象化を徹底する事は困難であり、もしもそれを進めるとすれば言葉はやがて解体され、文字の音を作品の主たる構成要素して扱う詩というメディウムの方へと向かう事となるでしょう。 小説」や「詩」などというジャンル的区分に本質的な意味を認めるべくもないですが、さしあたりこのような線引きは、近代以降、文学を考える上での前提だともいえます。未だその物語性を失っていないメディウムとしての文学。読者はいわば小説という「窓」を通じ、その世界観に触れる。できうる限りこの窓を磨き、透明化し、読者と外界との距離を近づけてゆく事こそが、良質な文学の一つの条件として認識されています。
ところが、福永信という小説家は様々な形で、このような小説の特性を切断する事を試みているように思えます。外界へ開かれた窓を傷つけ、あるいは何か別のものに入れ変えることによって、従来の小説の条件そのものを問おうとします。いわゆる「詩」的な実験において行われるような、言葉の文法的逸脱や、その音声的要素の強調が見られる訳でもなく、むしろ「小説」的な顔貌を常に装いながら、読者の知らぬ間に、何か別のものに変化させてしまっているかのようなのです。
彼のデヴュー短編集『アクロバット前夜』に所収された「読み終えて」を見てみましょう。
冒頭「君は、ねらわれている。」という宣言と共に書き始められるこの作品。「 君」は何らかの理由で何者かに狙われており、「僕」はその「君」へ向けて、仕掛けられた罠へ注意を払うよう、延々と長い手紙を書きます。「君」へと届けられたその手紙を読むように、読者は、小説を読み進める事となる、このような形式自体は夏目漱石「こころ」に代表されるように、珍しいものではありません、しかしながら、驚きは小説の終わりにやってきます。
「ここまで読んだ君になら僕の言おうとしていることがわかるだろう。この手紙の長さの意味がわかるだろう。この手紙を読んでいる間、君はその時間の分だけ、その日の、いつもの君の行動から遅れているのだ。その時間はただこれを読んでいた時間だ。そして読んでいた時間だけ、遅れた分だけ、予測され仕掛けられた罠を、ズラし、使いものにできなくするのだ。」(読み終えて)
「君」が手紙を読んでいた時間の消費こそが、この手紙が機能する唯一の効果なのであり、それ以外のものではない。手紙の中で延々と語られていた襲撃者の行為やそれに対する注意の喚起は、単に「読む」という行為を通じて現実的に時間を遅らせるためのものに他ならなかった。この時、小説内における「君」と読者との位置がピタリと一致します。手紙を読んでいた「君」へと与えられた時間の消費は、そっくりそのまま読者がそれまで小説を読んできた、その時間的消費へと重ねられます。透明な窓として物語を開示してきた小説が、突如、鏡へと変貌し、読者の姿、すなわち、いまここで私が読んでいる、その行為自体を強烈に映し出します。
読むことの意味が、端的に「時間稼ぎ」という目的に還元され、読んだ内容に先立つことを知らされたその時、小説の読者もまた、作品を読むために一定の時間を費やされていたという事実に蹴躓かされるでしょう。ここにおいて「読む」という経験は、小説を通じて外界ないし物語ではなく、読者自身がここで本を読んでいた、その現実的な時間の厚みこそを見させることとなるのです。
このような福永作品の「鏡」的傾向を示すために、もう一つの例を挙げておきましょう。短編集『コップとコッペパンとペン』所収の同名作品、その題の内には二つの「と」が含まれています。
早苗が図書館で見知らぬ男に話しかけられ緊張が高まったかと思えば、次の段落で彼らは夫婦となり早苗は妊娠している、と思えばすぐさま早苗は帰らぬ人となっており、早苗の娘は失踪した父を捜し始める。こういった具合に、小説内の諸出来事は十分な因果関係を欠いたまま接続されています。ここでは時間的、空間的な大きな飛躍が、その記述の分量と釣り合わない形で唐突に提示されている点に注視されなければなりません。先に記したような物語展開におけるあまりにも大きな文脈的飛躍は、複数の出来事間のズレ、その断面を読者に露にします。ある主体が何かを始めたかと思えば、その彼/彼女は消え去り、小説内の語りは、主要な主体をまた新たに見つけ出し、しかしその新たな主体もまた直ちに消え去り、小説はまた別の行為主体へと目を向けざるを得ない。ある主体「と」別の主体「と」、またさらに別の主体「と」…いうように、ここで見いだされるものは複数の人物と彼らをめぐる出来事間の断面、接続詞「と」そのものであり、確固たる主体が設定され得ない非人称的な次元というべきものなのです。
そもそもこの小説の題は「コップとコッペパンとペン」というのですが、これらの三つの要素のうちの二つは「いい湯だが電線は窓の外に延び、別の家に入り込み、そこにもまた、紙とペンとコップがある。この際どこも同じと言いたい。」という不可解な書き出しにおいて現れるものの、コッペパンというモチーフは一切、小説内に現れて来ない、むしろそれは純粋にコップ「と」ペン「と」をつなぐ音として挿入されているのだと考えるべきでしょうか。
コップとペンとをコッペパンがつなぐ。様々な主体が次々に移り行くこの小説において、様々に舞台は展開していくが、結局のところ「どこも同じ」。そこにあるのは登場人物でも、その背景となる場所でもない、単なるつなぎ目としての「と」、すなわち諸出来事間の蝶番のみなのです。このような、およそ一般的な意味においての小説の展開としては「不自然」な接続部の露呈は、読者の物語への感覚的没入を絶えず阻害し、読書という行為そのものへの認識へと、常に読者の意識を立ち返すことを強いるでしょう。眼前の小説、窓として本の向こうの世界を開いていた小説が、ここにおいて鏡へと姿を変え、読者の行為そのものを映して止まなくなるのです。
■ 笠島日記、遍在する窓としての
このように、読むことの行為それ自体を映し出す鏡としての小説を発表し続けてきた作家にして、この「笠島日記」は、非常に一般的な文学的特質、つまり外界を映す窓にも似た性質を保持しているように思えます。小説というものがある一定のフィクション性を前提とするならば、差し当たって日記文学や紀行文との類比で「普通」に読む事ができるでしょう。作家がフィルターとなって、我々読者は島で起こった出来事を知る、つまり、文章が透明な窓となり、読者を外界へと導いてゆく、というわけです。
しかし先述したように、この作家は小説の物語構造や物体的特性に対し極めて意識的な人間であり、そのような作家が、笠島日記が発表された媒体のあり方に対して無意識的であるはずもないでしょう。公開されたのはインターネットというメディウムであり、それはあらゆる場所から、この文章へとアクセスする事を可能にするものです。
小説家、福永信は2006年9月28日、十五日間の本島は笠島地区での滞在を開始します。当然の事ながら活動自体に何らかの成果を要請される、そのような与えられた役割に対する不安を隠そうともせず、インターネットを通じて、日記形式で公開してゆきます。
「いつもここで海を見ているんですか、と聞いてみる。滞在中は島の人たちと交流をもって下さいといわれているのである。『交流』といわれても全然絵が浮かばない。というか絵に描いたような交流の図しか浮かばす、右のような質問になったのだ。」(9/29の日記より)
滞在当初、大まかな活動プランのみを用意し島を訪れた福永は、交流のあり方そのものに多いに戸惑い、しかし、その戸惑いを孕んだ出来事そのものに何らかの意味を見いだすかのように、丹念に日記に書き付けてゆきます。ほとんど手ぶら状態でやってきた小説家の、その手持ち無沙汰な感覚、そして、何らかの結果が求められる状況への逡巡。そのような、何もない手ぶらな中から開始された笠島での滞在に何かしらの手応えを求めるかのように、人々との交流のかけらを収集してゆくことを思い立ちます。
「本島に入って三日目になって、ワークショップのプランを大幅に変えた。 (…) 実際にこの場所に来てみて、おじいさんおばあさんたちと言葉を交わすうちに、これはちがうな、集まって限定された時間の中で何か作業をする、そういうことではないなと思えてきた。(…)らくがき帳が置いてあるのがたまたま目にとまった。よし、これを使わせてもらおう。」
読者からすれば、なんとまあ行き当たりばったりな、と思う他ないのですが、ともかくもこのようにして、 らくがき帳の各ページに、ひらがな一文字を書いてもらう活動が開始されます。
画用紙に書かれてゆく数々のひらがな、それは島の中で福永信という人物を通じ、島民との対話、交流を通じて集められたものです。ひらがな一文字はそれ自体として何ら意味をもたず、あくまで断片に留まるほかない。さらに、小中学校では生徒と共に「音を撮る」というテーマのもとワークショップが行われ、インスタントカメラを手にした一人一人が、それぞれの視点で見つけ出した島の中の音のかけらを拾い集めてゆく。これらの経緯を記録し続けた「笠島日記」にもまた、島で起こる出来事のささいな断片が綴られ、少しずつ、日々記される分量も増えてゆきます。
「笠島日記」を通じて立ち現れるのは、福永という作家によって経験された、断片的な場所の記録なのであって、それが笠島という名と強く結びついて現れるという事はありません。そこで描かれる出来事は、まさに福永が「笠島日記を書き終えて」にて記しているように「どこにでもありそうな、そして実際にどこにだってある」ものなのでしょう。であるとすれば、インターネットという空間、どこからでもアクセスし得る空間に公開された日記を通じて私たちがたどり着く場所もまた、どこにでもありえる場所なのだと言えます。あらゆる場所に遍在する窓のむこうに「どこか」を見いだすこと、これこそがインターネット上で公開された「笠島日記」の特徴を為しており、それは一般的な小説の特性としての「窓」的な性質とも、福永の小説に見て取った「鏡」的な性質とも決定的に異なっています。
結ばれ、そして、ほどかれる
「笠島日記」追記の中で、この小説家は、なにやら重たい紙袋と共に本島へ再来するでしょう。作家の手にはワークショップに参加した生徒や先生たちに撮ってもらった数多くの写真、 十五日間の日記を凝縮した文章を一文字一ページにプリントアウトし、その所々に書いてもらったひらがなが散りばめられた全九巻もの手作り本。 無意味なまでに「重い」全九巻もの書物となった「笠島日記」は、原稿用紙五枚足らずの文章として編集されています。これらの公開と共に、普段ではあり得ないほど、島の内外から子供も大人もが集う、その祭りの日がやってくる。
このように2006年10月23日、二週間の滞在時に集められてきた写真、文字、そして日記までもが一点において交わり、凝集された。古い民家において古い人も新しい人もが集い、出会い、言葉を交わす、この出来事をさしあたりサイトスペシフィックだと考える事は可能でしょう。そうしたこの場所を特別なものとして見なすこともできるかもしれません。しかし、むしろ重要なのはその後、ここで集められたちいさな断片たちが、再び元の場所へと戻ってゆく、このことにあるのではないでしょうか。集められた写真は、撮影者それぞれが持ち帰り、出会いを通じて書かれた一つ一つのひらがなも、凝縮された日記と同様に、この場に集った読者の記憶のかけらなってバラバラに散逸してゆく。つかの間のにぎわいを見せたこの場所、真木邸にその後、何が残るという訳でもないのです。
結ばれた一点が、ここで再びほどかれる。いや、むしろそれは、ほどかれるためにこそ結ばれたのだと言うべきでしょう。そこにあったのは小さな、しかし、確かな波です。出来事のささやかな記憶のみを運び、何も残さず消え去ってしまうような波。そうしてこの場は、再び、「どこにでもありそうな、そして実際にどこにだってあるだろう」場所へと戻ってゆく。「笠島日記」はこのような、場所の遍在性へ向けて書かれていたのであり、その窓の向こうに見える、どこででもありうる場所へと読者を開いてゆくのです。これはサイトスペシフィックではない。あらゆる場所からあらゆる場所へ通じる窓、このような透明な窓こそが「アーティスト・イン・笠島」というプロジェクトがもたらした、目に見えない作品なのであり、 どこでもないが、しかしどこかに残された、唯一のものであるのかもしれません。
池田剛介
『これはサイトスペシフィックではない』
2006年十一月二十三日、私は丸亀からのフェリーに揺られ、本島という瀬戸内の小さな島を訪れました。島内の笠島地区でのアーティスト・イン・レジデンス成果発表会場へ向かう道すがら、私の頭にはすでに、「場所」とは何か、サイトスペシフィックとは何か、という問題が据えられていました。 作家がある「地域」へ出向き、「アーティスト・イン・レジデンス」しつつ、「ワークショップ」も催す、とこれだけの語が並べられれば誰でも、 少なくとも現代美術に関わっている人間にとっては誰でも、上のような問題を真っ先に思いつくことになります。ただ、そこに何らかの違和感がなかった訳ではなく、とりわけ福永信という名は、私の考える限り、サイトスペシフィックなる言葉——場の固有性と向かい合い、その特殊性を強調する、その語と容易に結びつくような対象ではありませんでした。
「笠島日記」、それを福永の作品として私が接した際、やはり同様の違和を感じざるを得ませんでした。私はこれまで、ある一定の関心を持って福永の小説に触れてきており、そのいくつかは別の場所で論じてもいます 。作家本人からは「事実として起こった事は小説に書かない」という事をよく聞いている、とすれば、ますますこのテクストは小説から遠ざかるように思えるでしょう。 にも関わらず、インターネット上に公開されていった日記は、単なる活動のルポタージュの枠を超え、彼の小説のあり方をも逆照射しているようにすら思えるのです。端的に言って、「笠島日記」は福永信のこれまでのテクストと決定的に違っています。この違いを見据えること、いわば前者と後者との視差を基に「アーティスト・イン・笠島」プロジェクトの意義を捉えること、これこそが本論の中で目指されています。
■ 鏡としての小説
通常の小説は、最良の作品に限られるであろうが、その作品を通じて外界をヴィヴィッドに映します。作家の感性を媒介として見られた世界が、紋切り型のイメージに回収される事なく生き生きと描写される時、読者は文字どおり本を「通じて」その構築された外界と接する事となります。このような特性は、少なくとも現代の表現としては、文学というメディウムに顕著なものだといえるでしょう。他の多くのメディア、例えば美術においては、20世紀を経て徹底した抽象化が進められてきており、外界を写し取る媒体としての特性は失ってゆきました。対して、文学は言葉を表現の手段として用いている限り、美術でいうような意味での抽象化を徹底する事は困難であり、もしもそれを進めるとすれば言葉はやがて解体され、文字の音を作品の主たる構成要素して扱う詩というメディウムの方へと向かう事となるでしょう。 小説」や「詩」などというジャンル的区分に本質的な意味を認めるべくもないですが、さしあたりこのような線引きは、近代以降、文学を考える上での前提だともいえます。未だその物語性を失っていないメディウムとしての文学。読者はいわば小説という「窓」を通じ、その世界観に触れる。できうる限りこの窓を磨き、透明化し、読者と外界との距離を近づけてゆく事こそが、良質な文学の一つの条件として認識されています。
ところが、福永信という小説家は様々な形で、このような小説の特性を切断する事を試みているように思えます。外界へ開かれた窓を傷つけ、あるいは何か別のものに入れ変えることによって、従来の小説の条件そのものを問おうとします。いわゆる「詩」的な実験において行われるような、言葉の文法的逸脱や、その音声的要素の強調が見られる訳でもなく、むしろ「小説」的な顔貌を常に装いながら、読者の知らぬ間に、何か別のものに変化させてしまっているかのようなのです。
彼のデヴュー短編集『アクロバット前夜』に所収された「読み終えて」を見てみましょう。
冒頭「君は、ねらわれている。」という宣言と共に書き始められるこの作品。「 君」は何らかの理由で何者かに狙われており、「僕」はその「君」へ向けて、仕掛けられた罠へ注意を払うよう、延々と長い手紙を書きます。「君」へと届けられたその手紙を読むように、読者は、小説を読み進める事となる、このような形式自体は夏目漱石「こころ」に代表されるように、珍しいものではありません、しかしながら、驚きは小説の終わりにやってきます。
「ここまで読んだ君になら僕の言おうとしていることがわかるだろう。この手紙の長さの意味がわかるだろう。この手紙を読んでいる間、君はその時間の分だけ、その日の、いつもの君の行動から遅れているのだ。その時間はただこれを読んでいた時間だ。そして読んでいた時間だけ、遅れた分だけ、予測され仕掛けられた罠を、ズラし、使いものにできなくするのだ。」(読み終えて)
「君」が手紙を読んでいた時間の消費こそが、この手紙が機能する唯一の効果なのであり、それ以外のものではない。手紙の中で延々と語られていた襲撃者の行為やそれに対する注意の喚起は、単に「読む」という行為を通じて現実的に時間を遅らせるためのものに他ならなかった。この時、小説内における「君」と読者との位置がピタリと一致します。手紙を読んでいた「君」へと与えられた時間の消費は、そっくりそのまま読者がそれまで小説を読んできた、その時間的消費へと重ねられます。透明な窓として物語を開示してきた小説が、突如、鏡へと変貌し、読者の姿、すなわち、いまここで私が読んでいる、その行為自体を強烈に映し出します。
読むことの意味が、端的に「時間稼ぎ」という目的に還元され、読んだ内容に先立つことを知らされたその時、小説の読者もまた、作品を読むために一定の時間を費やされていたという事実に蹴躓かされるでしょう。ここにおいて「読む」という経験は、小説を通じて外界ないし物語ではなく、読者自身がここで本を読んでいた、その現実的な時間の厚みこそを見させることとなるのです。
このような福永作品の「鏡」的傾向を示すために、もう一つの例を挙げておきましょう。短編集『コップとコッペパンとペン』所収の同名作品、その題の内には二つの「と」が含まれています。
早苗が図書館で見知らぬ男に話しかけられ緊張が高まったかと思えば、次の段落で彼らは夫婦となり早苗は妊娠している、と思えばすぐさま早苗は帰らぬ人となっており、早苗の娘は失踪した父を捜し始める。こういった具合に、小説内の諸出来事は十分な因果関係を欠いたまま接続されています。ここでは時間的、空間的な大きな飛躍が、その記述の分量と釣り合わない形で唐突に提示されている点に注視されなければなりません。先に記したような物語展開におけるあまりにも大きな文脈的飛躍は、複数の出来事間のズレ、その断面を読者に露にします。ある主体が何かを始めたかと思えば、その彼/彼女は消え去り、小説内の語りは、主要な主体をまた新たに見つけ出し、しかしその新たな主体もまた直ちに消え去り、小説はまた別の行為主体へと目を向けざるを得ない。ある主体「と」別の主体「と」、またさらに別の主体「と」…いうように、ここで見いだされるものは複数の人物と彼らをめぐる出来事間の断面、接続詞「と」そのものであり、確固たる主体が設定され得ない非人称的な次元というべきものなのです。
そもそもこの小説の題は「コップとコッペパンとペン」というのですが、これらの三つの要素のうちの二つは「いい湯だが電線は窓の外に延び、別の家に入り込み、そこにもまた、紙とペンとコップがある。この際どこも同じと言いたい。」という不可解な書き出しにおいて現れるものの、コッペパンというモチーフは一切、小説内に現れて来ない、むしろそれは純粋にコップ「と」ペン「と」をつなぐ音として挿入されているのだと考えるべきでしょうか。
コップとペンとをコッペパンがつなぐ。様々な主体が次々に移り行くこの小説において、様々に舞台は展開していくが、結局のところ「どこも同じ」。そこにあるのは登場人物でも、その背景となる場所でもない、単なるつなぎ目としての「と」、すなわち諸出来事間の蝶番のみなのです。このような、およそ一般的な意味においての小説の展開としては「不自然」な接続部の露呈は、読者の物語への感覚的没入を絶えず阻害し、読書という行為そのものへの認識へと、常に読者の意識を立ち返すことを強いるでしょう。眼前の小説、窓として本の向こうの世界を開いていた小説が、ここにおいて鏡へと姿を変え、読者の行為そのものを映して止まなくなるのです。
■ 笠島日記、遍在する窓としての
このように、読むことの行為それ自体を映し出す鏡としての小説を発表し続けてきた作家にして、この「笠島日記」は、非常に一般的な文学的特質、つまり外界を映す窓にも似た性質を保持しているように思えます。小説というものがある一定のフィクション性を前提とするならば、差し当たって日記文学や紀行文との類比で「普通」に読む事ができるでしょう。作家がフィルターとなって、我々読者は島で起こった出来事を知る、つまり、文章が透明な窓となり、読者を外界へと導いてゆく、というわけです。
しかし先述したように、この作家は小説の物語構造や物体的特性に対し極めて意識的な人間であり、そのような作家が、笠島日記が発表された媒体のあり方に対して無意識的であるはずもないでしょう。公開されたのはインターネットというメディウムであり、それはあらゆる場所から、この文章へとアクセスする事を可能にするものです。
小説家、福永信は2006年9月28日、十五日間の本島は笠島地区での滞在を開始します。当然の事ながら活動自体に何らかの成果を要請される、そのような与えられた役割に対する不安を隠そうともせず、インターネットを通じて、日記形式で公開してゆきます。
「いつもここで海を見ているんですか、と聞いてみる。滞在中は島の人たちと交流をもって下さいといわれているのである。『交流』といわれても全然絵が浮かばない。というか絵に描いたような交流の図しか浮かばす、右のような質問になったのだ。」(9/29の日記より)
滞在当初、大まかな活動プランのみを用意し島を訪れた福永は、交流のあり方そのものに多いに戸惑い、しかし、その戸惑いを孕んだ出来事そのものに何らかの意味を見いだすかのように、丹念に日記に書き付けてゆきます。ほとんど手ぶら状態でやってきた小説家の、その手持ち無沙汰な感覚、そして、何らかの結果が求められる状況への逡巡。そのような、何もない手ぶらな中から開始された笠島での滞在に何かしらの手応えを求めるかのように、人々との交流のかけらを収集してゆくことを思い立ちます。
「本島に入って三日目になって、ワークショップのプランを大幅に変えた。 (…) 実際にこの場所に来てみて、おじいさんおばあさんたちと言葉を交わすうちに、これはちがうな、集まって限定された時間の中で何か作業をする、そういうことではないなと思えてきた。(…)らくがき帳が置いてあるのがたまたま目にとまった。よし、これを使わせてもらおう。」
読者からすれば、なんとまあ行き当たりばったりな、と思う他ないのですが、ともかくもこのようにして、 らくがき帳の各ページに、ひらがな一文字を書いてもらう活動が開始されます。
画用紙に書かれてゆく数々のひらがな、それは島の中で福永信という人物を通じ、島民との対話、交流を通じて集められたものです。ひらがな一文字はそれ自体として何ら意味をもたず、あくまで断片に留まるほかない。さらに、小中学校では生徒と共に「音を撮る」というテーマのもとワークショップが行われ、インスタントカメラを手にした一人一人が、それぞれの視点で見つけ出した島の中の音のかけらを拾い集めてゆく。これらの経緯を記録し続けた「笠島日記」にもまた、島で起こる出来事のささいな断片が綴られ、少しずつ、日々記される分量も増えてゆきます。
「笠島日記」を通じて立ち現れるのは、福永という作家によって経験された、断片的な場所の記録なのであって、それが笠島という名と強く結びついて現れるという事はありません。そこで描かれる出来事は、まさに福永が「笠島日記を書き終えて」にて記しているように「どこにでもありそうな、そして実際にどこにだってある」ものなのでしょう。であるとすれば、インターネットという空間、どこからでもアクセスし得る空間に公開された日記を通じて私たちがたどり着く場所もまた、どこにでもありえる場所なのだと言えます。あらゆる場所に遍在する窓のむこうに「どこか」を見いだすこと、これこそがインターネット上で公開された「笠島日記」の特徴を為しており、それは一般的な小説の特性としての「窓」的な性質とも、福永の小説に見て取った「鏡」的な性質とも決定的に異なっています。
結ばれ、そして、ほどかれる
「笠島日記」追記の中で、この小説家は、なにやら重たい紙袋と共に本島へ再来するでしょう。作家の手にはワークショップに参加した生徒や先生たちに撮ってもらった数多くの写真、 十五日間の日記を凝縮した文章を一文字一ページにプリントアウトし、その所々に書いてもらったひらがなが散りばめられた全九巻もの手作り本。 無意味なまでに「重い」全九巻もの書物となった「笠島日記」は、原稿用紙五枚足らずの文章として編集されています。これらの公開と共に、普段ではあり得ないほど、島の内外から子供も大人もが集う、その祭りの日がやってくる。
このように2006年10月23日、二週間の滞在時に集められてきた写真、文字、そして日記までもが一点において交わり、凝集された。古い民家において古い人も新しい人もが集い、出会い、言葉を交わす、この出来事をさしあたりサイトスペシフィックだと考える事は可能でしょう。そうしたこの場所を特別なものとして見なすこともできるかもしれません。しかし、むしろ重要なのはその後、ここで集められたちいさな断片たちが、再び元の場所へと戻ってゆく、このことにあるのではないでしょうか。集められた写真は、撮影者それぞれが持ち帰り、出会いを通じて書かれた一つ一つのひらがなも、凝縮された日記と同様に、この場に集った読者の記憶のかけらなってバラバラに散逸してゆく。つかの間のにぎわいを見せたこの場所、真木邸にその後、何が残るという訳でもないのです。
結ばれた一点が、ここで再びほどかれる。いや、むしろそれは、ほどかれるためにこそ結ばれたのだと言うべきでしょう。そこにあったのは小さな、しかし、確かな波です。出来事のささやかな記憶のみを運び、何も残さず消え去ってしまうような波。そうしてこの場は、再び、「どこにでもありそうな、そして実際にどこにだってあるだろう」場所へと戻ってゆく。「笠島日記」はこのような、場所の遍在性へ向けて書かれていたのであり、その窓の向こうに見える、どこででもありうる場所へと読者を開いてゆくのです。これはサイトスペシフィックではない。あらゆる場所からあらゆる場所へ通じる窓、このような透明な窓こそが「アーティスト・イン・笠島」というプロジェクトがもたらした、目に見えない作品なのであり、 どこでもないが、しかしどこかに残された、唯一のものであるのかもしれません。
池田剛介
Posted by ギャラリーアルテ at 17:35│Comments(0)
│本島笠島地区アートプロジェクトWeb記録集