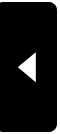2009年07月06日
ふるかはひでたか 『記憶のカケラ~本島 』



ふるかはひでたか 「記憶のかけら」
床(トコ)に立体、軸物、陶片によるインスタレーション、
本島の浜辺には、島の人々の暮らしを偲ばせる硝子や陶器のかけらがたくさん落ちている。ふるかはひでたかは、幾世代にも渡って波に洗われた陶片を拾い集め、数十種類の陶片を金継(*1)の技法でつなぎ合わせ、ひとつの器を形作った。陶片は江戸時代から明治、大正、昭和にかけてのものが多く見いだせる。福永信とは異なるアプローチによる島人の暮らし(記憶)の集積を想像させる作品。
*1[金継ぎ/金繕い]は、欠け、割れ、傷ついた陶磁器を漆で継ぎ、傷に純金で蒔絵を
して繕う伝統の技法
写真解説
真木邸の床の間 陶片を漆による金継を施し、形作られたひとつの立体作品。
陶片の制作模型図を色紙仕立てにした軸物。陶片で本島の島を形作ったインスタレーション。
『記憶のカケラ~本島 』
本島の浜辺を歩いていた。五月晴れに潮風が心地よい。
波打ち際で、貝などに混じって波に洗われる陶片を見た。砂に呉須の青が映えて美しい。幾つかそんな陶片を手にとって、浜に並べて見ていると、想像は勝手に巡りはじめる。
これらは島で使われた器か、それとも流れ着いた陶片だろうか…。恐らく、もともと異なる時代に別々の土地で作られたものだろう。そして様々な人の暮らしの中で、それぞれに物や思いを収めてきた器であったに違いない。
なんだか眺めるうちに、暮らしであるとか歴史といった、島を内から外から形作ってきた営みの、「記憶のカケラ」たちが浜に寄せ、ぐるりと島の輪郭を描いているような…そんな幻想にとらわれてくる。
突然、この陶片たちを呼び継いで、新たな器を作ったらどうだろう…なんて思いつきが頭をよぎった。
職人が土から作った器が、幾多の手を経て砕けたのち、今また島の浜で土に帰ろうとしている。そんな、過去の営みの痕跡を、新たな器として再生させるのだ。これは忘却過程にある記憶を編み直して、新たな歴史を作ることに近い。きっと出来た器は、島の姿を反映するものとなるだろう。
七月、プランを胸に再び本島を訪れた。浜を歩いて3kgにも及ぶ陶片を拾い集めた。それらを持ち帰った僕は、まるでパズルでも解くかのように器を拵えた。そうして出来た器には、そのまま島の名をつけた。
陶磁器に詳しい方に尋ねたところ、器の陶片には、明治期の印判染付や、江戸中期の伊万里などが見られるという。カケラたちはどんな記憶を語ってくれているのか。器は小さな空間を抱え、そこに収めるべき想像を待つようだ。
展覧会では、旧真木邸の床の間に器を据えた。隣りには、拾い集めた陶片の残り全てを用いて、本島の形を模った。もしも、展覧会を訪れた人のうち幾らかでも、島の経てきた年月や、そこに暮らした人々の面影を、この作品に夢見て頂くことができたならば、それに優る幸せはない。
Posted by ギャラリーアルテ at 13:01│Comments(0)
│本島笠島地区アートプロジェクトWeb記録集