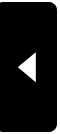2011年06月02日
企業メセナ協議会より 意見募集とのこと
お知らせします。
「文化芸術活動への助成に係る新たな審査・評価等の仕組みの
在り方について(報告書案)」に関する意見募集
意見募集期間は6月8日(水)までです。
芸術文化振興基金は、政府出資の541億円と、民間の出えん金112億円を原資
に運用。
幅広いご意見をお寄せください。
いかに転載
***************
平成23年6月1日日本芸術文化振興会
日本芸術文化振興会では、文化審議会文化政策部会の
「審議経過報告」を踏まえ、文化芸術活動への助成に関して、
専門家(プログラムオフィサー)を配置し、
現場の実情を把握した上で、専門的な審査・評価を行い、
文化芸術活動への助成に関するPDCAサイクルを確立する観点から審
査・評価の仕組みを導入するため、平成23年1月から「文化芸術活動へ
の助成に係る新たな審査・評価等に関する調査研究会(以下「調査研究
会」)を開催してまいりました。
この度、調査研究会において、これまでの議論の内容を報告書案として取
りまとめました。ついては、本件に関し、意見募集を実施いたします。
ご意見等がございましたら、下記の要領にてご掲出ください。
【1.具体的内容】
「文化芸術活動への助成に係る新たな審査・評価等の仕組みの在り方について(報告書案)」
(下記掲載)
【2.ご意見の提出について】
(1)提出手段 郵送・FAX・電子メール
(電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承ください)
(2)提出期限 平成23年6月8日(水)
(3)宛先 日本芸術文化振興会基金部芸術活動助成課 宛
住 所:〒102-8656 東京都千代田区隼町4-1
FAX:03-3265-7474
電子メールアドレス:geijutsu-nt@ntj.jac.go.jp
(電子メールでのご提出の際には、お手数ですが件名を「調査研究会報告
書案への意見」としてください。また、コンピューターウィルス対策の
ため添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文にご意見を
ご記入くださいますようお願い申し上げます。)
【3.提出様式について】
「調査研究会報告書案への意見」
・氏名
・性別・年齢
・職業(在学中の場合は「高校生」「大学生」など
在学する学校段階を表記。)
・住所
・電話番号
・ご意見
※複数の論点についてご意見をお寄せいただく場合には、
とりまとめの都合上、論点毎に別葉としてください。
(1枚1意見、1メール1意見としてください。)
【4.備考】
①ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、
あらかじめご了承願います。
②ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表されることがあります。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場
合の連絡以外の用途では使用しません。
お問い合わせ先
日本芸術文化振興会基金部芸術活動助成課
担 当 吉井、小畑
電 話 03-3265-6365
FAX 03-3265-7474.
平成23年6月1日(意見募集用)
文化芸術活動への助成に係る新たな審査・評価等の仕組みの在り方について
(報告書案)
1.はじめに
○文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次基本方針、
平成23年2月8日閣議決定)において、「文化芸術への支援策をより有効に
機能させるため、独立行政法人日本芸術文化振興会における専門家による
審査、事後評価、調査研究等の機能を大幅に強化し、諸外国のアーツカウン
シルに相当する新たな仕組みを導入する。このため、
早急に必要な調査研究を行うとともに、
可能なところから試行的な取組を実施する。」との方針が示された。
○本調査研究会においては、文化審議会における第3次基本方針の策定
に向けた審議を踏まえ、独立行政法人日本芸術文化振興会
(以下「振興会」という。)が行う文化芸術活動に対する助成事業を
より効果的なものとするため、専門的な知識や調査研究に基づ
く助言、情報提供等を行う「プログラムディレクター(以下「PD」という。)」
や「プログラムオフィサー(以下「PO」という。)」を活用した
審査・評価等の仕組みの在り方について、これまでに 回の会合を開催して
調査研究を重ねてきた。
○本調査研究会では、様々な関係団体や有識者からヒアリングを実施すると
ともに、民間における取組や英国の事例を参考にしつつ、事後評価の実施
や調査研究の充実、PD及びPOを活用した助成事業の改善の在り方、
PD及びPOの機能や役割、PD及びPOに望ましい人材等について検討を
行ってきた。
○本報告書は、本調査研究会における検討を踏まえ、平成23年度に試行
する新たな審査・評価等の仕組みの在り方等について示すとともに、それを
踏まえた将来における審査・評価等の仕組みの在り方について考えられる
方向性を示すものである。
現在の助成事業の審査・評価等に係る現状と課題
〔現 状〕
(振興会が実施する助成事業)
○現在、振興会においては、文化庁から交付される補助金により振興会が
実施する「トップレベルの舞台芸術創造事業1」と芸術文化振興基金の運
用益によって行う「芸術文化振興基金助成事業」という2つの助成事業を
行っている。
○
トップレベルの舞台芸術創造事業は、舞台芸術の水準向上の直接的な
牽引力となることが期待される芸術性の高い優れた芸術文化活動等を支
援するものである。また、芸術文化振興基金助成事業は、すべての国民が
芸術文化に親しみ、自らの手で新しい文化を創造するための環境の醸成
とその基盤の強化を図る観点から、芸術家及び芸術に関する団体が行う
芸術の創造又は普及を図るための活動等を継続的かつ安定的に
支援するものである。
(審査の仕組み)
○振興会では、助成金を適正に交付するため、外部有識者から構成される
芸術文化振興基金運営委員会(以下、「運営委員会」という。)を設置す
るとともに、各分野の実情及び特性に応じた審査を実施するため、運営委
員会のもとに、4の部会及び12の専門委員会を設置している。
○助成の決定に当たっては、振興会理事長が運営委員会に助成対象活動
及び助成金額について諮問を行い、これを受けて運営委員会において、
助成対象活動の募集や助成金交付の基本方針を決定するとともに、
部会及び専門委員会に対し順次、調査審議するよう付託する。
○これを受け、はじめに各専門委員会において、専門委員会ごとの審査の
方法等を定め、各専門委員が行う書面審査を経て、専門的見地から
合議により採択すべき助成対象活動を選定する。
○次に、部会において、専門委員会における審査結果をもとに、採択すべき
助成対象活動及び助成金額について審議を行い、運営委員会に報告する。
○運営委員会においては、採択すべき助成対象活動及び助成金額に係る
部会での審議結果を基に、助成対象活動及び助成金額を審議・決定し
、振興会理事長に答申する。
1舞台芸術の水準向上の直接的な牽引力となることが期待される芸術性
の高い優れた芸術文化活動等の支援は、平成23年度より「トップレベル
の舞台芸術創造事業」として実施され、これまで実施されてきた「芸術創
造活動特別推進事業」については、平成22年度限りの事業となっている。
2(参考) 現在の振興会における審査の仕組み
答申
報告
報告
芸術文化振興基金
運営委員会
(委員数14名)
部 会
(委員数24名)
専門委員会
(委員数91名)
助成対象活動の採否及び助成金額の審議
専門的見地から、助成金交付要望書の審査・助成対象活動の選定
付託
諮問
〔課 題〕
○ このような現在の審査の在り方については、以下に掲げるような様々な課
題が指摘されている。
・ 応募された活動を審査する委員(以下「審査委員」という。)は外部有識
者に委嘱し、公平性を担保するため3年程度で交代することとしているが、
審査に当たっての経験やノウハウが蓄積されにくい。
・ 審査委員の目に触れることが少ない設立間もない団体や地域の団体が
不利になる可能性がある。
・ 募集時に審査基準が明らかにされておらず、審査委員がどのような基準
で審査をしているのか不明瞭である。
・ 助成金額については、専門委員会においては審査されず、運営委員会
において決定されている。専門委員会において出された経費や積算等に関
する意見が、運営委員会において助成金額が決定されるまでの間、どのよ
うに反映されているのか分かりにくい。
・ 多数の要望書を限られた期間で審査2するために審査委員相互の十分
な意見交換が行われていない。
・ 審査結果については、現在、採択結果を公表しているが、不採択理由
については公表していないことから、不採択となった応募団体にとっては、改
善すべき点が明確ではなく、次回以降の応募に当たって参考とすることが困
難な状況にある。
・ 事後評価については、現在、専門委員会の委員及び振興会基金部の
事務職員(以下「基金部事務職員」という。)により公演調査を実施すると
ともに、助成対象団体に対し、公演終了後に実績報告書及び自己評価
書の提出を求めている。しかし、助成件数に対して公演調査の実施率は
低く3、東京に比べて地方の公演調査が少ない状況にある。
2 平成22年度の応募件数は1、629件(芸術創造活動特別推進事業
及び芸術文化振興基金助成事業)である。これらの応募については、
各専門委員による約1ヵ月間の事前の書面審査を経て、音楽、舞踊、
演劇第一、演劇第二及び伝統芸能・大衆芸能の各専門委員会において
1日から2日かけて合議による審査を行った。
3 平成21年度の調査実績は、助成金の交付件数が1、190件であった
のに対し、公演調査等の件数は342件である(芸術創造活動特別推進
事業及び芸術文化振興基金助成金)。
4・ また、事後評価に関する評価手法や評価基準が定型化されておらず、
助成効果についても詳細な分析や評価が十分になされていない。
・ 公演調査に係る調査報告書や、文化芸術団体等から提出された実績
報告書等の内容が次年度の審査に十分活用されていない。
・ さらに、助成対象分野の動向や、文化芸術団体等に関する公演実績、
受賞歴、財務状況等の基本的なデータの蓄積や分析も不十分である。
・ 文化芸術への支援策をより有効に機能させるためには、振興会が行う現
在の審査・評価等に係る機能の大幅な強化に加え、不断に助成事業の
改善を図ることが重要である。
3.新たな審査・評価等の仕組みの在り方について
○第3次基本方針を踏まえ、文化芸術活動への助成に係る計画、実行、
検証、改善サイクルを確立するため、振興会が行う審査、事後評価、調査
研究等の機能を大幅に強化する必要がある。
○具体的には、専門的な情報提供等を行うPD及びPOを配置し、的確な
情報に基づく審査、審査結果における採択理由及び助成により期待され
る効果の公表並びに不採択理由の伝達、事後評価の実施及び事後評
価を踏まえた次回以降の審査等が着実に実践されることが求められる。
○また、PD及びPOが持っている専門的知識や経験、PDを中心として行わ
れる調査研究によって得られた調査結果に基づき、振興会が行う文化芸
術活動に対する助成事業の改善を図ることが重要である。
○新たな審査・評価等の仕組みにおいては、PD及びPOが、その職務を円
滑に遂行するため、現地調査等においてPD及びPOをサポートする調査
員を活用することが必要である。
○これらを踏まえ、文化庁から交付される補助金により振興会が実施するトッ
プレベルの舞台芸術創造事業(以下「平成23年度における審査・評価等
の仕組みについて」において「事業」という。)のうち、平成23年度において
音楽及び舞踊の2分野において新たな審査・評価等の仕組みを試行する
に当たり、以下に示す方法で実施することを提言する。
5
≪平成23年度における審査・評価等の仕組みについて≫
①事業に係る基本的な方向性の提示
○振興会において、文化芸術活動に対し、より効果的な助成が行われるよう
にするため、事業を実施するに当たり、文化芸術の振興に関する基本的な
方針等に示されている国の政策や事業の目的を踏まえつつ、PDを中心に
これまでの音楽及び舞踊における事業の実績や課題について調査及び分
析する。
○このような調査及び分析を基に事業の対象である音楽及び舞踊において、
PD及びPOを中心とした事業に係る基本的な方向性を提示する。この基
本的な方向性については、専門委員会の審議を経て、運営委員会におい
て決定する。
②審査
○
審査は、従来の審査の仕組みを活用しつつ、PD及びPOの専門性を生か
して実施することとする。
(ⅰ)審査基準の作成
○審査における公正性が更に確保されるよう、PD及びPOの専門的な知識
や経験を生かし、助成の基本方針を踏まえた審査基準を作成し、専門委
員会における検討を経た上で運営委員会において決定することとする。
また、審査の透明性を高めるため、審査基準については、助成に係る募集
を行う際に併せて公表することとする。
(ⅱ)専門委員会
○現在、専門委員会においては、予め委員が、各自で書面審査を行った上
で、合議による審査を実施している。
○専門委員会における審査においては、PD及びPOが助成対象活動全般(
要望額を含む。)にわたり助言等を行い、審議を行うこととする。
(ⅲ)部会
○部会においては、専門委員会における指摘事項、その他PD及びPOから
の助言等を踏まえ、助成対象活動の審議、助成金額の審議、分野間の
調整等を行う。
6
(ⅳ)運営委員会
○運営委員会においては、部会や専門委員会における指摘事項、その他
PD及びPOからの助言等を踏まえ、助成対象活動及び助成金額につい
て審議及び決定し、振興会理事長に答申することとする。これを受け、
理事長が助成対象活動や助成金額を最終的に決定する。
③審査結果の公表等
○審査の透明性を確保するとともに、文化芸術団体が、それぞれの活動を更
に発展させることができるよう、助成対象活動ごとの採択の理由や助成によ
り期待される効果を公表することが必要であり、その方策を検討する。その
際、採択の理由や助成により期待される効果については、専門委員会等
における意見をとりまとめ、運営委員会において決定することとする。
○不採択となった助成対象活動を応募した団体が、今後の活動を行うに当
たり、事業の改善や見直しを行うための参考となるよう、原則として、当該
団体に対し、当該不採択理由を伝えることが必要であり、その方策を検討
する。その際、不採択となった理由については、専門委員会等における意
見をとりまとめ、運営委員会において決定することとする。
④事後評価
(ⅰ)事後評価の役割等
○事後評価は、助成した文化芸術活動が適切に実施されたかを確認すると
ともに、助成対象活動の分野においてどの程度の波及効果を及ぼしたかと
いう視点を含め、助成した文化芸術活動の成果を把握する役割を果たし
ている。
○これらの事後評価の役割を踏まえつつ、その実施方法については、事後評
価を行うことが目的化しないよう、ある程度手続きを簡素化する必要がある
。
(ⅱ)事後評価の方法
○事後評価の役割や事業の実施方法4等を踏まえ、PD及びPOの専門的
な知識や経験を生かし、事業に合った事後評価の方法を検討する。
4 トップレベルの舞台芸術創造事業については、来年度から公演単位支
援型の助成(公演1本毎の助成)と年間事業支援型の助成(複数年の継
続助成)の二種類の方法で実施される。 7
○その際、なるべく助成対象活動に係る一連の取組が把握できるよう、日頃
、文化芸術団体から聴取した情報、助成対象団体から提出される報告書
等も材料とすることを考慮する必要がある。
○事後評価の方法、評価基準及び事後評価の結果については、専門委員
会における検討を経た上で、運営委員会において決定する。なお、評価基
準を作成した場合には、公表する。
(ⅲ)事後評価の結果の活用
○事後評価の結果については、次回の助成対象活動の審査を行う場合に、
要望書と合わせて運営委員会等の各委員会(以下「各委員会」という。)
に提示する。各委員会の委員においては、事後評価結果を踏まえ、事業
の趣旨に照らし、引き続き当該活動に対し助成することが当該活動の分
野において有効であるか否かといった長期的な観点から審査を行うことが重
要である。
○事後評価の結果については、助成対象団体の今後の活動に資するよう、
助成対象団体に伝えるとともに、公表することが必要であり、その方策を検
討する。
⑤調査研究の充実
○振興会において、助成対象分野や文化芸術団体の実情を踏まえた審査
や、助成対象活動の事後評価、助成事業の改善等を着実に実施するた
め、助成対象分野や関係する文化芸術団体等に関する調査研究を充実
させることが必要である。
○調査研究については、文化芸術団体に関する実績、受賞歴及び財務状
況、助成対象分野に関する我が国及び諸外国の動向について情報を収
集及び分析するとともに、助成対象団体との意見交換等を通じて「見る側
・聴く側」の要望の把握に努める。
○POを中心に、助成対象となった公演に赴き、現地調査を行うとともに、適
宜助成対象団体との意見交換等を実施し、助成対象活動の進捗状況
を把握するとともに、必要な情報の収集に努める。
8
○ 現地調査については、PD及びPOだけですべての公演を調査することは
困難であることから、調査を行う際には必要に応じてPOの下に調査員を配
置し、調査員も活用してなるべく多くの公演に赴き、助成対象活動の進捗
状況の把握等に努める。
○ こうして収集した情報やデータ等については、活用しやすいよう、可能なと
ころからデータベース化を進める。
⑥事業の検証及び改善
○このような仕組みによる審査・評価等を実施していく中で、PDを中心として
、その実施状況や課題を検証する。
○併せて音楽や舞踊の分野における助成の状況及び事後評価結果を分析
した結果等を総合的に勘案して、事業に係る基本的な方向性の提示や
審査基準の見直しを行うとともに、必要に応じて、振興会が実施する事業
の改善に生かしていく必要がある。
4.PD及びPOの機能及び役割等
(1)PD及びPOの機能及び役割
○PD及びPOに期待される主な機能は、それぞれの専門性を生かすことに
より、対象分野への助成についての戦略を明確にするとともに、
審査及び評価において一層の公正性を高めることである。
○PD及びPOの役割は、審査・評価等に係る事務的な業務から助成対象
団体への助言や人の紹介、会計に係るノウハウの供与等連絡調整に係る
業務、助成成果の普及に係る業務、事業目標を達成するために必要な
調査研究まで多岐にわたる。
○PDの大きな役割の一つとして、国の政策や助成事業の目標を踏まえた上
で、運営委員会に対し、専門的な知識、経験及び調査研究結果の分析
等に基づいた助成事業に係る審査・評価等の仕組みについて改善を提言
すること及び事業目標の達成に向けた効果的な助成の在り方について提
言することが挙げられる。
○このほか、PO間の調整やPOの評価とともに、POが行う職務を統括するこ
とが挙げられる。
9
○POの主な役割は、調査研究を通じて、助成対象分野の状況を的確に把
握するとともに、専門的な知識、経験、調査研究から得たデータ等を新た
な審査・評価に適切に提供していくことなどである。
○POの具体的職務としては、以下のようなものが挙げられる。
〔募集〕
助成に係る基本的な方向性の検討
〔審査〕
審査基準案の作成
各委員会における助言及び情報提供(各分野の動向や応募団体に係る
情報、要望額の妥当性等)
採択理由及び期待される効果の整理
不採択理由の整理
〔事後評価〕
評価基準案の作成
助成対象活動の現地調査
助成対象団体との意見交換
事後評価案の作成
運営委員会及び専門委員会における事後評価結果案についての説明
〔調査研究等〕
担当分野の調査研究
助成対象団体の調査(助成対象団体に関する実績、受賞歴、財務状況
等のデータの収集・分析等)及び助成対象団体への助言
助成成果の分析・普及
助成事業の改善についてPDへの意見具申
○
PD及びPOは、審査及び事後評価の公正性を担保する観点から、審査
や事後評価に関する決定権を持たないこととする。
○
PD及びPOが上記の機能及び役割を果たすためには、その職務内容を明
確にする必要がある。
○
PD及びPOには、助成事業の目的を理解し、関係者との信頼関係を構
築することが求められる。このため、PD及びPOは、各委員会の委員や基
金部事務職員、文化芸術団体等と密に連携を図り、様々な情報交換、
意見調整を行いながら、担当する分野についての広く大きな立場からの視
点を持ち、戦略的、機動的に職務を遂行することが求められる。 10
○
振興会基金部においては、こうしたPD及びPOの機能及び役割を十分に
発揮できるように、この仕組みを運用することが求められる。
○
PD及びPOが、振興会が行う審査・評価等の仕組みについて改善の提言
を行うこと等により、振興会基金部全体の機能が強化されることにもつなが
ることを期待する。
(2)PD及びPOに求められる資質・能力等
○
PD及びPOには、その役割を果たすため、担当分野の状況や課題に精通
し、専門分野に係る知識、優れた見識を有することはもとより、審査・評価
に求められる情報提供や助成に係る方向性の検討等を行うことから、特定
の文化芸術団体等に偏ることのない公平な態度や助成事業の改善に係
る企画能力、審査・評価等に係る事務処理能力等が求められる。
○
PD及びPOは、日常的に文化芸術団体等と接触し、意見交換やヒアリン
グ等を行うことを通じて、審査・評価を実施するに当たり必要となる情報収
集を行うことから、高いコミュニケーション能力を備えていることが求められる。
○
PD及びPOについては、助成する側として助成を受ける文化芸術団体との
適切な距離間を保つ必要があり、自分の置かれた立場を理解し、対応で
きる社会的常識やバランス感覚を持っていることが求められる。
○
PDは、PO間の調整、POの評価のほか、POの職務を統括する役割を担
うことから、より広い視野と深い見識を持つこととともに、管理的能力を有す
ることが求められる。
○
PD及びPOがそれぞれの能力を十分に発揮するため、分野ごとにチームと
して能力の補完を図る必要がある。
○
POとなった人材についても、実践を通じて、実績を重ね、その能力を伸長
していく必要があるため、その任期等についても配慮することが重要である。
○
優れたPD及びPOを確保していくため、PD及びPOという職が、文化芸術
分野におけるキャリアパスとして位置づけられることが望まれる。
11
5.将来における審査・評価等の仕組みの在り方について
○ 本格的な導入に向けた第一歩として試行される平成23年度における審
査・評価等の仕組みの成果及び課題について、平成24年度以降フォロー
アップされ、引き続き将来における審査・評価等の仕組みの在り方について
検討されることが求められる。
○ PD及びPOを活用した審査・評価等の仕組みを本格的に導入するに
当たっては、文化庁及び振興会において、早期に対象分野を拡大するとと
もに、芸術文化振興基金助成事業等も対象とした制度にしていく必要が
ある。
○ その際、PD及びPOの配置の効果を確認するとともに、振興会において
、文化芸術活動に対する助成がより効果的に行われるようにするため、運
営委員会、部会、専門委員会及び振興会基金部の体制及び機能につ
いて検討することが重要である。
○ また、PD及びPOの配置に当たっては、PD及びPOがその機能及び役
割を更に発揮することができるよう、PD及びPOを常勤職員として振興会
に配置していくこととともに、分野ごとにPD及びPOを増員することが望まれ
る。
○ このほか、地域の文化芸術活動については、地域の実情を踏まえた助成
を行うための仕組みの在り方を検討することも考えられる。
12平成23年度における審査・評価等のスケジュールとPD及びPOの職務(イ
メージ)
≪PD及びPOの職務≫
平成23年
8月~9月
・事業の実績等の調査分析
・助成の基本的な方向性案
・審査基準案の作成
9月上旬 ○専門委員会の開催
・募集案内案
・助成金交付の基本方針案
・事業の実績等の調査分析
・助成の基本的な方向性案
・審査基準についての説明
・審査基準案について審議
○運営委員会の開催
・募集案内案
・助成金交付の基本方針案
・審査基準案について審議・決定
9月下旬 募集開始
11月中旬 募集締め切り
平成24年
1月上旬 ○専門委員会の委員による
・適宜、必要な情報等を提供
・専門委員会における指摘等を整理
・事後評価の方法について説明
専門委員会の委員の求めに応じ、必要な情報を提供
・適宜、必要な情報等を提供
・部会における指摘等を整理
応募内容について整理・分析
事後評価の方法を検討
~2月中旬 事前の書面審査
1月下旬 ○運営委員会の開催
・応募状況の報告
・助成金の分野別配分
について審議・決定
2月上旬 ○専門委員会の開催
~3月上旬 事前の書面審査結果
を基に合議により
・助成対象活動
・助成金額
・事後評価基準案
について審議
2月下旬 ○部会の開催
~3月上旬 ・助成対象活動
・助成金額
・分野間の調整等
について審議 13
・適宜、必要な情報等を提供
・採択理由の整理及び期待される効果を整理
・不採択理由を整理
・事後評価の方法について説明
3月中旬 ○運営委員会及び
部会長会議開催
・助成対象活動
・助成金額
・採択理由及び
期待される効果
・不採択理由
・事後評価基準案
について審議・決定
3月下旬 助成対象活動及び事後評価の
評価基準の公表
4月以降 振興会から随時、
・助成対象活動の実施時期に応じ、事後評価を実施
・助成対象活動を調査
・助成対象団体と意見を交換
・採択理由及び
期待される効果
について公表
・不採択理由
・担当分野の調査研究を実施
・助成対象団体を調査
・助成成果を分析・普及
について応募団体
に対し通知
平成25年4月
事後評価結果案の作成
14
平成25年9月 ○専門委員会の開催
平成24年度助成対象活動
に関する事後評価結果案等
事後評価結果案について説明
について審議
○運営委員会の開催
平成24年度助成対象活動
に関する事後評価結果案等
について審議・決定
その後 随時、振興会から事後評価結果を
助成対象団体に対し通知
「文化芸術活動への助成に係る新たな審査・評価等の仕組みの
在り方について(報告書案)」に関する意見募集
意見募集期間は6月8日(水)までです。
芸術文化振興基金は、政府出資の541億円と、民間の出えん金112億円を原資
に運用。
幅広いご意見をお寄せください。
いかに転載
***************
平成23年6月1日日本芸術文化振興会
日本芸術文化振興会では、文化審議会文化政策部会の
「審議経過報告」を踏まえ、文化芸術活動への助成に関して、
専門家(プログラムオフィサー)を配置し、
現場の実情を把握した上で、専門的な審査・評価を行い、
文化芸術活動への助成に関するPDCAサイクルを確立する観点から審
査・評価の仕組みを導入するため、平成23年1月から「文化芸術活動へ
の助成に係る新たな審査・評価等に関する調査研究会(以下「調査研究
会」)を開催してまいりました。
この度、調査研究会において、これまでの議論の内容を報告書案として取
りまとめました。ついては、本件に関し、意見募集を実施いたします。
ご意見等がございましたら、下記の要領にてご掲出ください。
【1.具体的内容】
「文化芸術活動への助成に係る新たな審査・評価等の仕組みの在り方について(報告書案)」
(下記掲載)
【2.ご意見の提出について】
(1)提出手段 郵送・FAX・電子メール
(電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承ください)
(2)提出期限 平成23年6月8日(水)
(3)宛先 日本芸術文化振興会基金部芸術活動助成課 宛
住 所:〒102-8656 東京都千代田区隼町4-1
FAX:03-3265-7474
電子メールアドレス:geijutsu-nt@ntj.jac.go.jp
(電子メールでのご提出の際には、お手数ですが件名を「調査研究会報告
書案への意見」としてください。また、コンピューターウィルス対策の
ため添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文にご意見を
ご記入くださいますようお願い申し上げます。)
【3.提出様式について】
「調査研究会報告書案への意見」
・氏名
・性別・年齢
・職業(在学中の場合は「高校生」「大学生」など
在学する学校段階を表記。)
・住所
・電話番号
・ご意見
※複数の論点についてご意見をお寄せいただく場合には、
とりまとめの都合上、論点毎に別葉としてください。
(1枚1意見、1メール1意見としてください。)
【4.備考】
①ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、
あらかじめご了承願います。
②ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表されることがあります。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場
合の連絡以外の用途では使用しません。
お問い合わせ先
日本芸術文化振興会基金部芸術活動助成課
担 当 吉井、小畑
電 話 03-3265-6365
FAX 03-3265-7474.
平成23年6月1日(意見募集用)
文化芸術活動への助成に係る新たな審査・評価等の仕組みの在り方について
(報告書案)
1.はじめに
○文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次基本方針、
平成23年2月8日閣議決定)において、「文化芸術への支援策をより有効に
機能させるため、独立行政法人日本芸術文化振興会における専門家による
審査、事後評価、調査研究等の機能を大幅に強化し、諸外国のアーツカウン
シルに相当する新たな仕組みを導入する。このため、
早急に必要な調査研究を行うとともに、
可能なところから試行的な取組を実施する。」との方針が示された。
○本調査研究会においては、文化審議会における第3次基本方針の策定
に向けた審議を踏まえ、独立行政法人日本芸術文化振興会
(以下「振興会」という。)が行う文化芸術活動に対する助成事業を
より効果的なものとするため、専門的な知識や調査研究に基づ
く助言、情報提供等を行う「プログラムディレクター(以下「PD」という。)」
や「プログラムオフィサー(以下「PO」という。)」を活用した
審査・評価等の仕組みの在り方について、これまでに 回の会合を開催して
調査研究を重ねてきた。
○本調査研究会では、様々な関係団体や有識者からヒアリングを実施すると
ともに、民間における取組や英国の事例を参考にしつつ、事後評価の実施
や調査研究の充実、PD及びPOを活用した助成事業の改善の在り方、
PD及びPOの機能や役割、PD及びPOに望ましい人材等について検討を
行ってきた。
○本報告書は、本調査研究会における検討を踏まえ、平成23年度に試行
する新たな審査・評価等の仕組みの在り方等について示すとともに、それを
踏まえた将来における審査・評価等の仕組みの在り方について考えられる
方向性を示すものである。
現在の助成事業の審査・評価等に係る現状と課題
〔現 状〕
(振興会が実施する助成事業)
○現在、振興会においては、文化庁から交付される補助金により振興会が
実施する「トップレベルの舞台芸術創造事業1」と芸術文化振興基金の運
用益によって行う「芸術文化振興基金助成事業」という2つの助成事業を
行っている。
○
トップレベルの舞台芸術創造事業は、舞台芸術の水準向上の直接的な
牽引力となることが期待される芸術性の高い優れた芸術文化活動等を支
援するものである。また、芸術文化振興基金助成事業は、すべての国民が
芸術文化に親しみ、自らの手で新しい文化を創造するための環境の醸成
とその基盤の強化を図る観点から、芸術家及び芸術に関する団体が行う
芸術の創造又は普及を図るための活動等を継続的かつ安定的に
支援するものである。
(審査の仕組み)
○振興会では、助成金を適正に交付するため、外部有識者から構成される
芸術文化振興基金運営委員会(以下、「運営委員会」という。)を設置す
るとともに、各分野の実情及び特性に応じた審査を実施するため、運営委
員会のもとに、4の部会及び12の専門委員会を設置している。
○助成の決定に当たっては、振興会理事長が運営委員会に助成対象活動
及び助成金額について諮問を行い、これを受けて運営委員会において、
助成対象活動の募集や助成金交付の基本方針を決定するとともに、
部会及び専門委員会に対し順次、調査審議するよう付託する。
○これを受け、はじめに各専門委員会において、専門委員会ごとの審査の
方法等を定め、各専門委員が行う書面審査を経て、専門的見地から
合議により採択すべき助成対象活動を選定する。
○次に、部会において、専門委員会における審査結果をもとに、採択すべき
助成対象活動及び助成金額について審議を行い、運営委員会に報告する。
○運営委員会においては、採択すべき助成対象活動及び助成金額に係る
部会での審議結果を基に、助成対象活動及び助成金額を審議・決定し
、振興会理事長に答申する。
1舞台芸術の水準向上の直接的な牽引力となることが期待される芸術性
の高い優れた芸術文化活動等の支援は、平成23年度より「トップレベル
の舞台芸術創造事業」として実施され、これまで実施されてきた「芸術創
造活動特別推進事業」については、平成22年度限りの事業となっている。
2(参考) 現在の振興会における審査の仕組み
答申
報告
報告
芸術文化振興基金
運営委員会
(委員数14名)
部 会
(委員数24名)
専門委員会
(委員数91名)
助成対象活動の採否及び助成金額の審議
専門的見地から、助成金交付要望書の審査・助成対象活動の選定
付託
諮問
〔課 題〕
○ このような現在の審査の在り方については、以下に掲げるような様々な課
題が指摘されている。
・ 応募された活動を審査する委員(以下「審査委員」という。)は外部有識
者に委嘱し、公平性を担保するため3年程度で交代することとしているが、
審査に当たっての経験やノウハウが蓄積されにくい。
・ 審査委員の目に触れることが少ない設立間もない団体や地域の団体が
不利になる可能性がある。
・ 募集時に審査基準が明らかにされておらず、審査委員がどのような基準
で審査をしているのか不明瞭である。
・ 助成金額については、専門委員会においては審査されず、運営委員会
において決定されている。専門委員会において出された経費や積算等に関
する意見が、運営委員会において助成金額が決定されるまでの間、どのよ
うに反映されているのか分かりにくい。
・ 多数の要望書を限られた期間で審査2するために審査委員相互の十分
な意見交換が行われていない。
・ 審査結果については、現在、採択結果を公表しているが、不採択理由
については公表していないことから、不採択となった応募団体にとっては、改
善すべき点が明確ではなく、次回以降の応募に当たって参考とすることが困
難な状況にある。
・ 事後評価については、現在、専門委員会の委員及び振興会基金部の
事務職員(以下「基金部事務職員」という。)により公演調査を実施すると
ともに、助成対象団体に対し、公演終了後に実績報告書及び自己評価
書の提出を求めている。しかし、助成件数に対して公演調査の実施率は
低く3、東京に比べて地方の公演調査が少ない状況にある。
2 平成22年度の応募件数は1、629件(芸術創造活動特別推進事業
及び芸術文化振興基金助成事業)である。これらの応募については、
各専門委員による約1ヵ月間の事前の書面審査を経て、音楽、舞踊、
演劇第一、演劇第二及び伝統芸能・大衆芸能の各専門委員会において
1日から2日かけて合議による審査を行った。
3 平成21年度の調査実績は、助成金の交付件数が1、190件であった
のに対し、公演調査等の件数は342件である(芸術創造活動特別推進
事業及び芸術文化振興基金助成金)。
4・ また、事後評価に関する評価手法や評価基準が定型化されておらず、
助成効果についても詳細な分析や評価が十分になされていない。
・ 公演調査に係る調査報告書や、文化芸術団体等から提出された実績
報告書等の内容が次年度の審査に十分活用されていない。
・ さらに、助成対象分野の動向や、文化芸術団体等に関する公演実績、
受賞歴、財務状況等の基本的なデータの蓄積や分析も不十分である。
・ 文化芸術への支援策をより有効に機能させるためには、振興会が行う現
在の審査・評価等に係る機能の大幅な強化に加え、不断に助成事業の
改善を図ることが重要である。
3.新たな審査・評価等の仕組みの在り方について
○第3次基本方針を踏まえ、文化芸術活動への助成に係る計画、実行、
検証、改善サイクルを確立するため、振興会が行う審査、事後評価、調査
研究等の機能を大幅に強化する必要がある。
○具体的には、専門的な情報提供等を行うPD及びPOを配置し、的確な
情報に基づく審査、審査結果における採択理由及び助成により期待され
る効果の公表並びに不採択理由の伝達、事後評価の実施及び事後評
価を踏まえた次回以降の審査等が着実に実践されることが求められる。
○また、PD及びPOが持っている専門的知識や経験、PDを中心として行わ
れる調査研究によって得られた調査結果に基づき、振興会が行う文化芸
術活動に対する助成事業の改善を図ることが重要である。
○新たな審査・評価等の仕組みにおいては、PD及びPOが、その職務を円
滑に遂行するため、現地調査等においてPD及びPOをサポートする調査
員を活用することが必要である。
○これらを踏まえ、文化庁から交付される補助金により振興会が実施するトッ
プレベルの舞台芸術創造事業(以下「平成23年度における審査・評価等
の仕組みについて」において「事業」という。)のうち、平成23年度において
音楽及び舞踊の2分野において新たな審査・評価等の仕組みを試行する
に当たり、以下に示す方法で実施することを提言する。
5
≪平成23年度における審査・評価等の仕組みについて≫
①事業に係る基本的な方向性の提示
○振興会において、文化芸術活動に対し、より効果的な助成が行われるよう
にするため、事業を実施するに当たり、文化芸術の振興に関する基本的な
方針等に示されている国の政策や事業の目的を踏まえつつ、PDを中心に
これまでの音楽及び舞踊における事業の実績や課題について調査及び分
析する。
○このような調査及び分析を基に事業の対象である音楽及び舞踊において、
PD及びPOを中心とした事業に係る基本的な方向性を提示する。この基
本的な方向性については、専門委員会の審議を経て、運営委員会におい
て決定する。
②審査
○
審査は、従来の審査の仕組みを活用しつつ、PD及びPOの専門性を生か
して実施することとする。
(ⅰ)審査基準の作成
○審査における公正性が更に確保されるよう、PD及びPOの専門的な知識
や経験を生かし、助成の基本方針を踏まえた審査基準を作成し、専門委
員会における検討を経た上で運営委員会において決定することとする。
また、審査の透明性を高めるため、審査基準については、助成に係る募集
を行う際に併せて公表することとする。
(ⅱ)専門委員会
○現在、専門委員会においては、予め委員が、各自で書面審査を行った上
で、合議による審査を実施している。
○専門委員会における審査においては、PD及びPOが助成対象活動全般(
要望額を含む。)にわたり助言等を行い、審議を行うこととする。
(ⅲ)部会
○部会においては、専門委員会における指摘事項、その他PD及びPOから
の助言等を踏まえ、助成対象活動の審議、助成金額の審議、分野間の
調整等を行う。
6
(ⅳ)運営委員会
○運営委員会においては、部会や専門委員会における指摘事項、その他
PD及びPOからの助言等を踏まえ、助成対象活動及び助成金額につい
て審議及び決定し、振興会理事長に答申することとする。これを受け、
理事長が助成対象活動や助成金額を最終的に決定する。
③審査結果の公表等
○審査の透明性を確保するとともに、文化芸術団体が、それぞれの活動を更
に発展させることができるよう、助成対象活動ごとの採択の理由や助成によ
り期待される効果を公表することが必要であり、その方策を検討する。その
際、採択の理由や助成により期待される効果については、専門委員会等
における意見をとりまとめ、運営委員会において決定することとする。
○不採択となった助成対象活動を応募した団体が、今後の活動を行うに当
たり、事業の改善や見直しを行うための参考となるよう、原則として、当該
団体に対し、当該不採択理由を伝えることが必要であり、その方策を検討
する。その際、不採択となった理由については、専門委員会等における意
見をとりまとめ、運営委員会において決定することとする。
④事後評価
(ⅰ)事後評価の役割等
○事後評価は、助成した文化芸術活動が適切に実施されたかを確認すると
ともに、助成対象活動の分野においてどの程度の波及効果を及ぼしたかと
いう視点を含め、助成した文化芸術活動の成果を把握する役割を果たし
ている。
○これらの事後評価の役割を踏まえつつ、その実施方法については、事後評
価を行うことが目的化しないよう、ある程度手続きを簡素化する必要がある
。
(ⅱ)事後評価の方法
○事後評価の役割や事業の実施方法4等を踏まえ、PD及びPOの専門的
な知識や経験を生かし、事業に合った事後評価の方法を検討する。
4 トップレベルの舞台芸術創造事業については、来年度から公演単位支
援型の助成(公演1本毎の助成)と年間事業支援型の助成(複数年の継
続助成)の二種類の方法で実施される。 7
○その際、なるべく助成対象活動に係る一連の取組が把握できるよう、日頃
、文化芸術団体から聴取した情報、助成対象団体から提出される報告書
等も材料とすることを考慮する必要がある。
○事後評価の方法、評価基準及び事後評価の結果については、専門委員
会における検討を経た上で、運営委員会において決定する。なお、評価基
準を作成した場合には、公表する。
(ⅲ)事後評価の結果の活用
○事後評価の結果については、次回の助成対象活動の審査を行う場合に、
要望書と合わせて運営委員会等の各委員会(以下「各委員会」という。)
に提示する。各委員会の委員においては、事後評価結果を踏まえ、事業
の趣旨に照らし、引き続き当該活動に対し助成することが当該活動の分
野において有効であるか否かといった長期的な観点から審査を行うことが重
要である。
○事後評価の結果については、助成対象団体の今後の活動に資するよう、
助成対象団体に伝えるとともに、公表することが必要であり、その方策を検
討する。
⑤調査研究の充実
○振興会において、助成対象分野や文化芸術団体の実情を踏まえた審査
や、助成対象活動の事後評価、助成事業の改善等を着実に実施するた
め、助成対象分野や関係する文化芸術団体等に関する調査研究を充実
させることが必要である。
○調査研究については、文化芸術団体に関する実績、受賞歴及び財務状
況、助成対象分野に関する我が国及び諸外国の動向について情報を収
集及び分析するとともに、助成対象団体との意見交換等を通じて「見る側
・聴く側」の要望の把握に努める。
○POを中心に、助成対象となった公演に赴き、現地調査を行うとともに、適
宜助成対象団体との意見交換等を実施し、助成対象活動の進捗状況
を把握するとともに、必要な情報の収集に努める。
8
○ 現地調査については、PD及びPOだけですべての公演を調査することは
困難であることから、調査を行う際には必要に応じてPOの下に調査員を配
置し、調査員も活用してなるべく多くの公演に赴き、助成対象活動の進捗
状況の把握等に努める。
○ こうして収集した情報やデータ等については、活用しやすいよう、可能なと
ころからデータベース化を進める。
⑥事業の検証及び改善
○このような仕組みによる審査・評価等を実施していく中で、PDを中心として
、その実施状況や課題を検証する。
○併せて音楽や舞踊の分野における助成の状況及び事後評価結果を分析
した結果等を総合的に勘案して、事業に係る基本的な方向性の提示や
審査基準の見直しを行うとともに、必要に応じて、振興会が実施する事業
の改善に生かしていく必要がある。
4.PD及びPOの機能及び役割等
(1)PD及びPOの機能及び役割
○PD及びPOに期待される主な機能は、それぞれの専門性を生かすことに
より、対象分野への助成についての戦略を明確にするとともに、
審査及び評価において一層の公正性を高めることである。
○PD及びPOの役割は、審査・評価等に係る事務的な業務から助成対象
団体への助言や人の紹介、会計に係るノウハウの供与等連絡調整に係る
業務、助成成果の普及に係る業務、事業目標を達成するために必要な
調査研究まで多岐にわたる。
○PDの大きな役割の一つとして、国の政策や助成事業の目標を踏まえた上
で、運営委員会に対し、専門的な知識、経験及び調査研究結果の分析
等に基づいた助成事業に係る審査・評価等の仕組みについて改善を提言
すること及び事業目標の達成に向けた効果的な助成の在り方について提
言することが挙げられる。
○このほか、PO間の調整やPOの評価とともに、POが行う職務を統括するこ
とが挙げられる。
9
○POの主な役割は、調査研究を通じて、助成対象分野の状況を的確に把
握するとともに、専門的な知識、経験、調査研究から得たデータ等を新た
な審査・評価に適切に提供していくことなどである。
○POの具体的職務としては、以下のようなものが挙げられる。
〔募集〕
助成に係る基本的な方向性の検討
〔審査〕
審査基準案の作成
各委員会における助言及び情報提供(各分野の動向や応募団体に係る
情報、要望額の妥当性等)
採択理由及び期待される効果の整理
不採択理由の整理
〔事後評価〕
評価基準案の作成
助成対象活動の現地調査
助成対象団体との意見交換
事後評価案の作成
運営委員会及び専門委員会における事後評価結果案についての説明
〔調査研究等〕
担当分野の調査研究
助成対象団体の調査(助成対象団体に関する実績、受賞歴、財務状況
等のデータの収集・分析等)及び助成対象団体への助言
助成成果の分析・普及
助成事業の改善についてPDへの意見具申
○
PD及びPOは、審査及び事後評価の公正性を担保する観点から、審査
や事後評価に関する決定権を持たないこととする。
○
PD及びPOが上記の機能及び役割を果たすためには、その職務内容を明
確にする必要がある。
○
PD及びPOには、助成事業の目的を理解し、関係者との信頼関係を構
築することが求められる。このため、PD及びPOは、各委員会の委員や基
金部事務職員、文化芸術団体等と密に連携を図り、様々な情報交換、
意見調整を行いながら、担当する分野についての広く大きな立場からの視
点を持ち、戦略的、機動的に職務を遂行することが求められる。 10
○
振興会基金部においては、こうしたPD及びPOの機能及び役割を十分に
発揮できるように、この仕組みを運用することが求められる。
○
PD及びPOが、振興会が行う審査・評価等の仕組みについて改善の提言
を行うこと等により、振興会基金部全体の機能が強化されることにもつなが
ることを期待する。
(2)PD及びPOに求められる資質・能力等
○
PD及びPOには、その役割を果たすため、担当分野の状況や課題に精通
し、専門分野に係る知識、優れた見識を有することはもとより、審査・評価
に求められる情報提供や助成に係る方向性の検討等を行うことから、特定
の文化芸術団体等に偏ることのない公平な態度や助成事業の改善に係
る企画能力、審査・評価等に係る事務処理能力等が求められる。
○
PD及びPOは、日常的に文化芸術団体等と接触し、意見交換やヒアリン
グ等を行うことを通じて、審査・評価を実施するに当たり必要となる情報収
集を行うことから、高いコミュニケーション能力を備えていることが求められる。
○
PD及びPOについては、助成する側として助成を受ける文化芸術団体との
適切な距離間を保つ必要があり、自分の置かれた立場を理解し、対応で
きる社会的常識やバランス感覚を持っていることが求められる。
○
PDは、PO間の調整、POの評価のほか、POの職務を統括する役割を担
うことから、より広い視野と深い見識を持つこととともに、管理的能力を有す
ることが求められる。
○
PD及びPOがそれぞれの能力を十分に発揮するため、分野ごとにチームと
して能力の補完を図る必要がある。
○
POとなった人材についても、実践を通じて、実績を重ね、その能力を伸長
していく必要があるため、その任期等についても配慮することが重要である。
○
優れたPD及びPOを確保していくため、PD及びPOという職が、文化芸術
分野におけるキャリアパスとして位置づけられることが望まれる。
11
5.将来における審査・評価等の仕組みの在り方について
○ 本格的な導入に向けた第一歩として試行される平成23年度における審
査・評価等の仕組みの成果及び課題について、平成24年度以降フォロー
アップされ、引き続き将来における審査・評価等の仕組みの在り方について
検討されることが求められる。
○ PD及びPOを活用した審査・評価等の仕組みを本格的に導入するに
当たっては、文化庁及び振興会において、早期に対象分野を拡大するとと
もに、芸術文化振興基金助成事業等も対象とした制度にしていく必要が
ある。
○ その際、PD及びPOの配置の効果を確認するとともに、振興会において
、文化芸術活動に対する助成がより効果的に行われるようにするため、運
営委員会、部会、専門委員会及び振興会基金部の体制及び機能につ
いて検討することが重要である。
○ また、PD及びPOの配置に当たっては、PD及びPOがその機能及び役
割を更に発揮することができるよう、PD及びPOを常勤職員として振興会
に配置していくこととともに、分野ごとにPD及びPOを増員することが望まれ
る。
○ このほか、地域の文化芸術活動については、地域の実情を踏まえた助成
を行うための仕組みの在り方を検討することも考えられる。
12平成23年度における審査・評価等のスケジュールとPD及びPOの職務(イ
メージ)
≪PD及びPOの職務≫
平成23年
8月~9月
・事業の実績等の調査分析
・助成の基本的な方向性案
・審査基準案の作成
9月上旬 ○専門委員会の開催
・募集案内案
・助成金交付の基本方針案
・事業の実績等の調査分析
・助成の基本的な方向性案
・審査基準についての説明
・審査基準案について審議
○運営委員会の開催
・募集案内案
・助成金交付の基本方針案
・審査基準案について審議・決定
9月下旬 募集開始
11月中旬 募集締め切り
平成24年
1月上旬 ○専門委員会の委員による
・適宜、必要な情報等を提供
・専門委員会における指摘等を整理
・事後評価の方法について説明
専門委員会の委員の求めに応じ、必要な情報を提供
・適宜、必要な情報等を提供
・部会における指摘等を整理
応募内容について整理・分析
事後評価の方法を検討
~2月中旬 事前の書面審査
1月下旬 ○運営委員会の開催
・応募状況の報告
・助成金の分野別配分
について審議・決定
2月上旬 ○専門委員会の開催
~3月上旬 事前の書面審査結果
を基に合議により
・助成対象活動
・助成金額
・事後評価基準案
について審議
2月下旬 ○部会の開催
~3月上旬 ・助成対象活動
・助成金額
・分野間の調整等
について審議 13
・適宜、必要な情報等を提供
・採択理由の整理及び期待される効果を整理
・不採択理由を整理
・事後評価の方法について説明
3月中旬 ○運営委員会及び
部会長会議開催
・助成対象活動
・助成金額
・採択理由及び
期待される効果
・不採択理由
・事後評価基準案
について審議・決定
3月下旬 助成対象活動及び事後評価の
評価基準の公表
4月以降 振興会から随時、
・助成対象活動の実施時期に応じ、事後評価を実施
・助成対象活動を調査
・助成対象団体と意見を交換
・採択理由及び
期待される効果
について公表
・不採択理由
・担当分野の調査研究を実施
・助成対象団体を調査
・助成成果を分析・普及
について応募団体
に対し通知
平成25年4月
事後評価結果案の作成
14
平成25年9月 ○専門委員会の開催
平成24年度助成対象活動
に関する事後評価結果案等
事後評価結果案について説明
について審議
○運営委員会の開催
平成24年度助成対象活動
に関する事後評価結果案等
について審議・決定
その後 随時、振興会から事後評価結果を
助成対象団体に対し通知
Posted by ギャラリーアルテ at 20:38│Comments(0)
│art