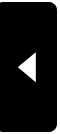2010年04月21日
日本文化の形成 宮本常一
現場にしかないものがあるし、繰り返し調査をしないと見えてこないものがある。
只今、宮本常一氏による『日本文化の形成』を読んでいる。
宮本常一の最晩年の観文研での講義録と遺稿集から成る「日本文化の形成」は
未刊ではあるけれども、研究されてこられた思いが盛り込まれた到達点となる一書だ。
氏は広い調査、フィールドワークを積み重ね、民俗・民具資料についての深い造詣を持つ。
その人が文献に接したときに、どれほど豊かなものをそこから汲みとり、
またそれに触発されることによって、文献のみに閉じこもっている研究者には
到底思いつくことのできない、すぐれた新しい発想を展開する。
□人は古来より移動しつづけていたという点
さらに
この本では現在日本というひとつの国とみられているこの国が
かつては明らかに東北日本と西南日本で明らかに違う文化をもっていたことにも言及され、興味ふかい。
□海洋民としての倭人
文化はその技術のみで別の地域に伝わるのではなく、
その技術を有した人びととともに移動するという考えが氏の発想の根底にある。
大陸文化が海を越えるためには船を必要とするが、
大陸人は海に親しみがすくなく船の建造技術ももっていなかった。
そこで大陸と日本列島の文化の橋渡しを倭人が担う。
この倭人は縄文人の後裔ではなく、日本に稲作をもたらした南方の海洋民だろうと宮本さんはいう。
海洋民である南方民族の温かい気候での住居形態―高床式で、
壁をもたない柱のみの住居がその後の日本語の住宅となっていくという仮説。
温かい気候でこそ快適であった壁なしの住宅が、
日本の南方にくらべれば寒い気候でも移入されているという視点だ。
御簾や簾、蔀戸といった壁の代わりをなす間仕切りを用いる住居形態が、
南方の海洋民ゆずりとしている視点。
宮本常一の旅行日数約4000日、通過した町村3000、
足をとどめて話を聞いた箇所800、民家にとめてもらうことおよそ1000軒。
対象があり、対話の姿が示唆に富む。
現場にしかないものがあるし、繰り返し調査をしないと見えてこないものはある。
日本を形づくった『記憶の文化』をイメージしようとする人がどのくらいいるのだろう。
(網野善彦解説より引用)
近年の考古学の発掘成果によって、列島の社会はただ一方的に朝鮮半島・中国大陸の文化を受容してきただけでなく、済州島などを媒介として双方の間で活発な交流が展開しており、また西方からだけでなく、北方世界・南方世界との交流もまた「日本文化」にとって重要な意味を持っていたことが明らかにされつつあるが、宮本氏は早くもそれを見通し、これまでとは大きく異なる、まさしく海を通じての各地域の内外の交流の中で、「日本文化」をとらえようとしているのである。
それは列島の諸地域のそれぞれに形成された豊かな個性を明らかにする道をひらき、とかく大和、京都、あるいは鎌倉などの政治の中心から歴史を見がちだった日本史像、水田の開かれた地域を先進地域とし、山や海に関わる地域を頭から後進地域と見る日本社会像を根本的に修正する確固たる視点を築くことになっているが、これはくまなく列島の各地を歩いてきた宮本氏によってはじめてなしえたことといえよう。
只今、宮本常一氏による『日本文化の形成』を読んでいる。
宮本常一の最晩年の観文研での講義録と遺稿集から成る「日本文化の形成」は
未刊ではあるけれども、研究されてこられた思いが盛り込まれた到達点となる一書だ。
氏は広い調査、フィールドワークを積み重ね、民俗・民具資料についての深い造詣を持つ。
その人が文献に接したときに、どれほど豊かなものをそこから汲みとり、
またそれに触発されることによって、文献のみに閉じこもっている研究者には
到底思いつくことのできない、すぐれた新しい発想を展開する。
□人は古来より移動しつづけていたという点
さらに
この本では現在日本というひとつの国とみられているこの国が
かつては明らかに東北日本と西南日本で明らかに違う文化をもっていたことにも言及され、興味ふかい。
□海洋民としての倭人
文化はその技術のみで別の地域に伝わるのではなく、
その技術を有した人びととともに移動するという考えが氏の発想の根底にある。
大陸文化が海を越えるためには船を必要とするが、
大陸人は海に親しみがすくなく船の建造技術ももっていなかった。
そこで大陸と日本列島の文化の橋渡しを倭人が担う。
この倭人は縄文人の後裔ではなく、日本に稲作をもたらした南方の海洋民だろうと宮本さんはいう。
海洋民である南方民族の温かい気候での住居形態―高床式で、
壁をもたない柱のみの住居がその後の日本語の住宅となっていくという仮説。
温かい気候でこそ快適であった壁なしの住宅が、
日本の南方にくらべれば寒い気候でも移入されているという視点だ。
御簾や簾、蔀戸といった壁の代わりをなす間仕切りを用いる住居形態が、
南方の海洋民ゆずりとしている視点。
宮本常一の旅行日数約4000日、通過した町村3000、
足をとどめて話を聞いた箇所800、民家にとめてもらうことおよそ1000軒。
対象があり、対話の姿が示唆に富む。
現場にしかないものがあるし、繰り返し調査をしないと見えてこないものはある。
日本を形づくった『記憶の文化』をイメージしようとする人がどのくらいいるのだろう。
(網野善彦解説より引用)
近年の考古学の発掘成果によって、列島の社会はただ一方的に朝鮮半島・中国大陸の文化を受容してきただけでなく、済州島などを媒介として双方の間で活発な交流が展開しており、また西方からだけでなく、北方世界・南方世界との交流もまた「日本文化」にとって重要な意味を持っていたことが明らかにされつつあるが、宮本氏は早くもそれを見通し、これまでとは大きく異なる、まさしく海を通じての各地域の内外の交流の中で、「日本文化」をとらえようとしているのである。
それは列島の諸地域のそれぞれに形成された豊かな個性を明らかにする道をひらき、とかく大和、京都、あるいは鎌倉などの政治の中心から歴史を見がちだった日本史像、水田の開かれた地域を先進地域とし、山や海に関わる地域を頭から後進地域と見る日本社会像を根本的に修正する確固たる視点を築くことになっているが、これはくまなく列島の各地を歩いてきた宮本氏によってはじめてなしえたことといえよう。
Posted by ギャラリーアルテ at 22:09│Comments(0)
│art
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。