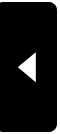2009年05月08日
ボイス_エンデ_ネグリ=ハート_ジャック・アタリ
 ギャラリーアルテは、一応コマーシャルギャラリーなので、所属作家の作品を販売するために、毎年アートフェア東京に出展している。ここ2.3年国内では、様々な形のアートフェアが開催され、活発な取引が行われている。
ギャラリーアルテは、一応コマーシャルギャラリーなので、所属作家の作品を販売するために、毎年アートフェア東京に出展している。ここ2.3年国内では、様々な形のアートフェアが開催され、活発な取引が行われている。リーマンショック以降のアートフェアということで、今年は思い切ったことをやろうと、いろいろ戦略を立てながら出展した。
3日間で来場(45000人)で、アートバブルだった去年よりも多い。日本とくに東京だが、アートが定着してきたことは実感した。今年はとくに投機目的で作品を購入するのではなく、美術愛好家による購入が目立つ、これは確かに好ましいことだが、それにしても、コレクターの眼はあまりいいとはいえないのではないかと感じる。フェア向きの作品というものがあって、画廊もそれは割り切って商いを行っている。
 アルテのブースでは、糸崎公朗『フォトモ』『デジワイド』、吉峯和美『interior』シリーズ、そして彦坂尚嘉の『皇居美術館空想』と『見立て茄子、赤茄子』を展示した。こちらは、地方都市丸亀からの出展なので、画廊のコンセプトを伝えることに主力を注ぐ。
アルテのブースでは、糸崎公朗『フォトモ』『デジワイド』、吉峯和美『interior』シリーズ、そして彦坂尚嘉の『皇居美術館空想』と『見立て茄子、赤茄子』を展示した。こちらは、地方都市丸亀からの出展なので、画廊のコンセプトを伝えることに主力を注ぐ。アート界は、東高西低。関西以西の出展は丸亀のアルテのみ。ちなみに対岸の岡山から備前焼の画廊が出展している。国内外から143画廊。国内最大のアートフェアである。
名古屋、大阪、奈良の画廊も東京へ移転するという。アルテは、四国に拠点を構えて、がんばって行くのだが、これは狭き門より入るという仕儀で、楽ではない。聖書に「狭き門より入れ」とあるが、こういうときは感覚が鋭敏で、作品もよく見えてくる。それにアイデアもいろいろ浮かぶ。
海外へ作家を打ち出して行かなければならないことは、痛感している。一方で自国の資産でもある作品を海外へ流出させるだけではなく、国内で理解を示し、作家を支援していただくコレクターを得るための努力も画廊の重要な仕事である。
アートフェアに出展している画廊には、海外も含めて様々なアートフェアに出展を促すオファーが届く。
昨年秋以降ヨーロッパやアメリカのフェアは閑散として、かなり厳しい結果が出たようだが、今年も上海、北京、シンガポール
とアートフェアへの案内が届いている。シンガポールは出展を考えていたが、新型インフルエンザのことも考えると、グローバルな経済の行く末とアートのグローバルな動きについて、様々思いをめぐらせる。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ドイツのアーティストヨゼフ・ボイスの『芸術と政治をめぐる』論考。
ミヒャエル・エンデの遺した現代の貨幣システムについての考察から、誕生している様々な地域経済への模索
ネグリ=ハート 国民国家の主権はどのように次のステージに進んでいけばいいのかを問う『帝国』
ジャック・アタリ市場主義を批判した『アンチ・エコノミクス』(1974)自律監視社会と自慰商品社会を根底から批評した『カニバリズムの秩序』(1979)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Posted by ギャラリーアルテ at 13:32│Comments(0)
│art