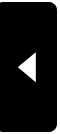2009年07月19日
ことばを訊ねて、資本主義のひみつ
買う 売る
買という言葉は
中国ではもともと同じ言葉。
「買」の意味は、あるものと別のものを取り替える意味である「貿」を語源としている。
はじめはボウと発音されていたが、後になってバイと発音されるようになった。
売るという意味には、「買」
という字にものを差し出すという意味の「出」を組み合わせて「賣」となり、
「売」は「賣」の略字体。
日本語ではどうか・・
買ふ 交ふ(かふ)の他動の意味か
交ひ、替ひ、買ひ という漢字の表記があてられている。
岩波の「古語辞典」では、甲乙の不達の別のものが互いに入れ違う意味という説明。
日本語においても
買うという言葉は、もともとは売り買い両方の意味をもっていた。
単にあるものと別のものを交換することをさしていたに過ぎない。
売るという言葉と区別されて、お金をはらって
モノを手に入れる行為を示すことになったのは、
時代もはるかに下ってのこと。
20世紀の最大の言語学者エミール・バンヴェニスト著
「インド=ヨーロッパの諸制度語彙集」(1969年)の経済語彙集は
この事実の解明の書
それではドイツ語においては・・
売る を意味する 「verkaufen 」は
「買う」を意味するkaufen から 派生した言葉であり
ギリシャ語の「借りる」を意味するdaneizomai は
「貸す」を意味するdaneizo という言葉から派生したと記述している。
資本主義の基本原理は、
差異から利潤を創り出す ということ。
古い形態の商業資本主義は、海を隔てた遠隔地との交易を媒介に
国内市場との差異から利潤を得る。
産業革命以降の資本主義の形態 産業資本主義は
農村などの過剰人口によって、構造的に作り出してきた
労働力の価値と労働生産性とのあいだの差異から利潤を得た。
遠隔地も農村の過剰人口もうしないつつある現代の資本主義は
差異そのものを意識的に創り出して行くことにある。
それが情報の商品化としての差異を創出にほかならない。
差異が利潤をつくり出す・・資本主義の基本原理のひみつ
買という言葉は
中国ではもともと同じ言葉。
「買」の意味は、あるものと別のものを取り替える意味である「貿」を語源としている。
はじめはボウと発音されていたが、後になってバイと発音されるようになった。
売るという意味には、「買」
という字にものを差し出すという意味の「出」を組み合わせて「賣」となり、
「売」は「賣」の略字体。
日本語ではどうか・・
買ふ 交ふ(かふ)の他動の意味か
交ひ、替ひ、買ひ という漢字の表記があてられている。
岩波の「古語辞典」では、甲乙の不達の別のものが互いに入れ違う意味という説明。
日本語においても
買うという言葉は、もともとは売り買い両方の意味をもっていた。
単にあるものと別のものを交換することをさしていたに過ぎない。
売るという言葉と区別されて、お金をはらって
モノを手に入れる行為を示すことになったのは、
時代もはるかに下ってのこと。
20世紀の最大の言語学者エミール・バンヴェニスト著
「インド=ヨーロッパの諸制度語彙集」(1969年)の経済語彙集は
この事実の解明の書
それではドイツ語においては・・
売る を意味する 「verkaufen 」は
「買う」を意味するkaufen から 派生した言葉であり
ギリシャ語の「借りる」を意味するdaneizomai は
「貸す」を意味するdaneizo という言葉から派生したと記述している。
資本主義の基本原理は、
差異から利潤を創り出す ということ。
古い形態の商業資本主義は、海を隔てた遠隔地との交易を媒介に
国内市場との差異から利潤を得る。
産業革命以降の資本主義の形態 産業資本主義は
農村などの過剰人口によって、構造的に作り出してきた
労働力の価値と労働生産性とのあいだの差異から利潤を得た。
遠隔地も農村の過剰人口もうしないつつある現代の資本主義は
差異そのものを意識的に創り出して行くことにある。
それが情報の商品化としての差異を創出にほかならない。
差異が利潤をつくり出す・・資本主義の基本原理のひみつ
Posted by ギャラリーアルテ at 14:13│Comments(3)
│art
この記事へのコメント
おはようございます。
この流れからすると、当然、「情報の差異が現代の~」みたいなところから、続けて行くことになるのでしょうかねえ。
あれから、彦坂さんのブログはときどきチェックしてます。
41次元とか想像界とか象徴界とかいうところの解説って、どっかにあるんでしょうか?
ハイアート型とかデザイン型とか、読んでると、だいたいつながってきそうなんですが。
この流れからすると、当然、「情報の差異が現代の~」みたいなところから、続けて行くことになるのでしょうかねえ。
あれから、彦坂さんのブログはときどきチェックしてます。
41次元とか想像界とか象徴界とかいうところの解説って、どっかにあるんでしょうか?
ハイアート型とかデザイン型とか、読んでると、だいたいつながってきそうなんですが。
Posted by たみ家 at 2009年07月20日 08:39
at 2009年07月20日 08:39
 at 2009年07月20日 08:39
at 2009年07月20日 08:39たみ屋さん
おはようございます。
ポストモダンです。近代を支えてきた大きな物語にたいする信頼が失われた時代が現在です。「社会の情報化」といわれた、知の形成や教養が不可分であるという考えは、既に衰退して、省みられていませんね。古い考え方となっているのです。
ポストモダンの時代は、知は交換されるもの、知そのものが目的とされない、知は他の物と交換するためのものとなっているようです。
彦坂さんの言う、過去に戻りつつ新しく拓くという表現は
とてもうなづけるものです。
41次元の解説あります。ラカンの判定法をモデルにしたものです。【アートの格付け】は言語判定法を使ったものです。言語判定法というのは、言語と現実の対応関係を逆転させることで、言語によって作品の質や性格を測定する技術です。
「格付け」は《超1流》から《41流》まであって、《41流》が下品の限界です。《超1流》が鑑賞構造の領域です。全部はまだ解明されていないのですが、主なものは下記のようです。
《超1流》狂気をも含む鑑賞構造美領域
《1流》理性美領域
《2流》技術美領域
《3流》ポップス美領域
《4流》不条理美領域
《5流》居住美領域
《6流》自然美領域
《7流》ビジネス美領域
《8流》信仰美領域
《11流》交通通信美領域
《13流》漫画コメディ美領域
《15流》葬儀美領域
《16流》崩壊美領域
《21流》性美領域
《22流》食美領域
《40流》スポーツ美領域
《41流》戦争美領域
おはようございます。
ポストモダンです。近代を支えてきた大きな物語にたいする信頼が失われた時代が現在です。「社会の情報化」といわれた、知の形成や教養が不可分であるという考えは、既に衰退して、省みられていませんね。古い考え方となっているのです。
ポストモダンの時代は、知は交換されるもの、知そのものが目的とされない、知は他の物と交換するためのものとなっているようです。
彦坂さんの言う、過去に戻りつつ新しく拓くという表現は
とてもうなづけるものです。
41次元の解説あります。ラカンの判定法をモデルにしたものです。【アートの格付け】は言語判定法を使ったものです。言語判定法というのは、言語と現実の対応関係を逆転させることで、言語によって作品の質や性格を測定する技術です。
「格付け」は《超1流》から《41流》まであって、《41流》が下品の限界です。《超1流》が鑑賞構造の領域です。全部はまだ解明されていないのですが、主なものは下記のようです。
《超1流》狂気をも含む鑑賞構造美領域
《1流》理性美領域
《2流》技術美領域
《3流》ポップス美領域
《4流》不条理美領域
《5流》居住美領域
《6流》自然美領域
《7流》ビジネス美領域
《8流》信仰美領域
《11流》交通通信美領域
《13流》漫画コメディ美領域
《15流》葬儀美領域
《16流》崩壊美領域
《21流》性美領域
《22流》食美領域
《40流》スポーツ美領域
《41流》戦争美領域
Posted by ソフィア at 2009年07月20日 12:33
ソフィアさん
こんばんは。
「知は交換されるもの、知そのものが目的とされない、知は他の物と交換するためのもの」
って、ことは、知は財なのか?財の価値を増幅させるものなのか?財の交換手段を上手くやる能力なのか?
ポストモダン思想を勉強してないたみ家が文面だけから判断したら、そういう風に思えました。
確かに、知は財であり、財の価値を増幅させたり、知のある人間が財の交換手段を操っているってのは、周囲の観察からあるとは思います。
ああ、勉強がしたい。
ああ、読書がしたい。
なのに、うどんは年中無休化に向かってるという矛盾。
それにしても、ソフィアさんも彦坂さんも、現代美術関係者は、いろいろ勉強されてる方が多いんですねえ。
時代が進むに従って、美術と知が結びつかざるを得なくなった背景があるのでしょうか?
だいたいは想像はしてるんですが、思い込みでは良くないと思い訊いてみたく思いました。
こんばんは。
「知は交換されるもの、知そのものが目的とされない、知は他の物と交換するためのもの」
って、ことは、知は財なのか?財の価値を増幅させるものなのか?財の交換手段を上手くやる能力なのか?
ポストモダン思想を勉強してないたみ家が文面だけから判断したら、そういう風に思えました。
確かに、知は財であり、財の価値を増幅させたり、知のある人間が財の交換手段を操っているってのは、周囲の観察からあるとは思います。
ああ、勉強がしたい。
ああ、読書がしたい。
なのに、うどんは年中無休化に向かってるという矛盾。
それにしても、ソフィアさんも彦坂さんも、現代美術関係者は、いろいろ勉強されてる方が多いんですねえ。
時代が進むに従って、美術と知が結びつかざるを得なくなった背景があるのでしょうか?
だいたいは想像はしてるんですが、思い込みでは良くないと思い訊いてみたく思いました。
Posted by たみ家 at 2009年07月20日 22:16
at 2009年07月20日 22:16
 at 2009年07月20日 22:16
at 2009年07月20日 22:16